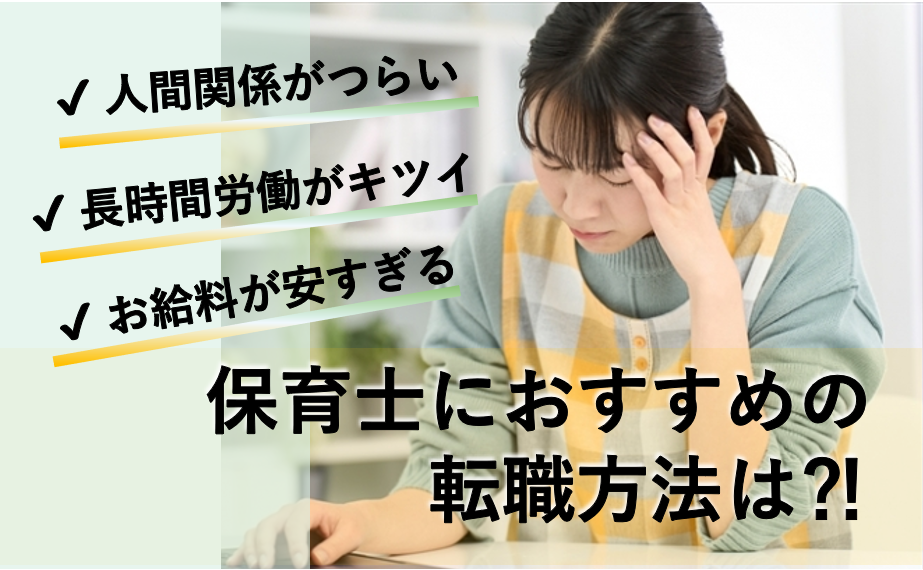※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
こんにちは! 現役保育士はなえみです。
(転職でホワイト園に巡り会えました!→ プロフィールはこちら)。
「お給料が安いな~」「転職しようかな~」って悩んでませんか?
それなら転職を有利にするために、「プラスαの資格」を取ってみるのはどうでしょう。
もちろん、転職は考えていない人でも、新たな資格取得はおススメです。
この記事では、「保育士資格にプラスαすると役立つおススメ資格10選」を解説。
保育士が取得すると役立つ資格で、比較的取りやすいものを選んでみました。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
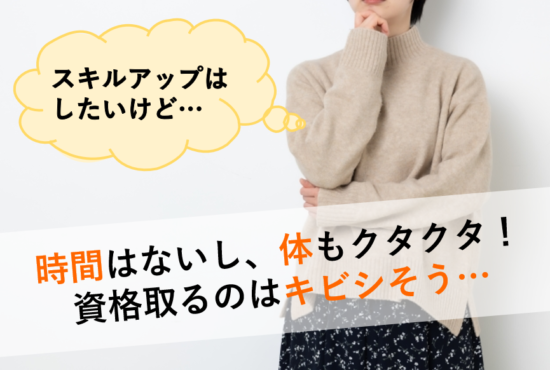
- お給料、安すぎ…! だから、資格を取って手当てを増やしたい!
- でも、残業や持ち帰り仕事で、家で勉強する時間なんかない
資格を取ってスキルアップしたいと思っても、実際にチャレンジするのは難しい…。
だったら、まずは転職してお給料を上げる方が手っ取り早いです。
それにホワイト園に転職すれば、資格を取るための勉強時間だって作れますよ。
保育士転職サイトに相談して、プライベートの時間が取れる職場を探してもらいましょう。
中でも、保育士バンクは私もおすすめのサイト。
あなたの希望を叶えるために、一歩進んでみませんか。
目次
転職にはプラスαの資格が強みになる!
転職を考えているなら、プラスαの資格を取ると強みになります。
なぜなら、資格っていうのは、その分野の勉強を積み重ねて習得したことの証だから。
それに、「目標のために努力ができる」ってこともアピールできます。
そんな向上心を持って積極的に行動できる人って、誰が見ても魅力的です。
「ぜひうちの園で力を発揮してほしい!」と思ってもらえますよ。
転職抜きでも資格を取るのはアリ!
一方、転職を考えていなくても、プラスαの資格を取るのは大いにアリ。
たとえば、保育士として働いていると、いろんな悩みが出てきますよね。
- 「もっと子どもの心を知りたい」
- 「得意なピアノをもっと活かしたい」
- 「活動のネタを増やしたい」
などの思いが出てきてるのかも。
それは、あなたが保育士として成長してきた証拠。
「今の自分に足りないものを埋めたい」「もっと成長したい」という気持ちなのでは?
それはとても素晴らしいことですよね。
新しい勉強ができたら、今より保育の引き出しが増えて視野が広がります。
保育士として、さらに成長していけますよ。
保育士資格にプラスαしたいおススメ資格10選!
それでは、「保育士資格にプラスαしたいおススメ資格」を10個紹介しますね。
調べてみると、保育士の仕事に関連がありそうな資格ってけっこうたくさんある。
でも、保育園で働きながら資格を取るのって、時間的にも体力的にもなかなかタイヘンです。
たとえば、「5日間泊りがけで取る資格」なんていうのは、現実的に難しいですよね。
また、保育園の現場で活かしにくい資格もありました。
なので、私は、たくさんの資格の中から、
- 比較的短時間、短期間でとれるもの
- 保育の現場で活かせるもの
- 保育士の方が実際に働きながら取得している
といった資格だけを10個選んでみました。↓
- リトミック指導員
- 認定病児保育スペシャリスト
- 絵本専門士
- こども環境管理士
- 幼児安全法指導員
- 運動保育士
- 幼児教育・保育英語検定
- おもちゃコンサルタント
- 保育ソーシャルワーカー
- 認定心理士
あなたの興味のある物はありそうでしょうか?
では、一つずつ見ていきましょう。
1 リトミック指導員
リトミック指導員とは、リトミックの専門知識と技術を持ち指導できる人のことです。
保育士なら知っているとは思いますが、リトミックとは、
「歌や音楽を通して、子ども達の感受性や集中力、そして社会性を育む」
ことをねらいとした指導法のこと。
特に、「歌やピアノが得意」といった保育士の方にはピッタリの資格ですね。
もちろん、資格がなくて歌ったり踊ったりするだけでも、子どもたちは十分楽しめます。
でも、リトミック指導員の知識とスキルがあれば、根拠を持った音楽活動ができますよね。
音楽や楽器を使った活動のレパートリーが確実に増えます。
そんなリトミック指導員の資格は、民間のリトミック指導員養成機関で取ります。
たとえば、ある養成機関では、
「年間9回(1回3時間)の講習を受けることで初級指導者資格が取れる」
といった感じ。
これぐらいなら、なんとか働きながらでも受講できそうですよね。
その養成講座では、2年目、3年目と受講を重ねていくことで、指導者としてのレベルがアップ。
リトミック指導員は、保育の中ですぐに活かせる資格だと思いますよ。
リトミック指導員になれる【特定非営利活動法人 リトミック研究センター】はこちら
2 認定病児保育スペシャリスト
認定病児保育スペシャリストとは、病気の子どもを保育するプロ。
これも民間の資格です。
「一般財団法人 日本病児保育協会」が認定する、日本初の資格なんですよ。
たとえば、預かっている子どもが急に熱を出すことってありますよね。
そんなときも、病児保育の専門知識がや対処術が身についていたら、落ち着いて対処できます。
園としても、そんな人材は欲しいはずで、とても重宝されます。
一般の保育園だけでなく、病児保育をしている園への転職もしやすくて確実に有利です。
認定病児保育スペシャリストは、保育士、病児保育従事者、看護師などが受講しています。
取得の流れとしては、
「Web上の講座全13回(1講座15分)を受講」
↓
「一次試験を受けてパス」
↓
「病児保育施設での実習(24時間以上)またはオンライン実習」
↓
「認定試験(1月と7月の年2回)」
となっています。
資格取得までには最短で1か月、平均で2か月ほどで実習まで終えられます。
これなら、なかなか時間が取れない保育士の方も取りやすいですよね。
非常時に大いに役立つ、認定病児保育スペシャリストの資格に、ぜひ挑戦してみては?
認定病児保育スペシャリストになれる【(財)日本病児保育協会 認定病児保育スペシャリスト】はこちら
3 絵本専門士
絵本専門士とは、「国立青少年教育振興機構」が創設した絵本の専門家を認定する資格。
具体的には、
「絵本に関する繊細な感性があり、多様な知識、扱い方を身につけた専門家」
であることを証明する資格です。
絵本というと、保育士にとってはとても身近なもの。
「子どもに読み聞かせるのが好きだし得意」という方も多いですよね。
それだけに、「簡単に取れそう」なんて思うかも。
でも、絵本専門士になるその過程は、意外に大変なんですよ。
ますは、絵本専門士養成講座を受けるのには、このような受講資格が設けられています。↓
- 子どもや絵本に関連する資格を有する者
- 絵本に関わる実務について、3年以上の経験が有る者
- 絵本に関わる活動に携わり、3年以上の経験がある者
- 絵本学や児童文学、美術について研究実績を有する者
保育士であれば1か2に当てはまるので、とりあえずクリアできると思います。
でも、次の関門としてこの受講者は、選考を通らないとダメなんですよ。
選考に通って初めて絵本専門士養成講座を受けられるんですね。
授業は、30コマ(1コマ90~120分で全50時間程度)を受けます。
一クラスが約30名の定員で、きめ細かい指導がされています。
まずは、絵本に関係する講義や演習。
基礎的なことから発展的な内容まで幅広く学びます。
さらに、絵本専門士になった時をイメージしてのディスカッションも。
そんなすべての授業を受け終わったら、さらに修了課題にチャレンジします。
この修了課題で絵本専門士としての資質や実力を評価されます。
最後に、絵本専門士委員会で絵本専門士と認められて、ようやく認定証をゲット。
そうして、晴れて絵本専門士としてあなたの名前が登録されます。
絵本専門士のホームページ上にもあなたの名前が載りますよ。
こう見てくると関門がいくつかあって、なんだかハードルが高い感じがしちゃいますね。
でも、それだけに取得できれば重みがあります。
絵本は、言語力や理解力、想像力などを育み、子どもたちの感性を磨いてくれるツール。
だからこそ、適切に扱って子どもたちに提供できる指導力が必要です。
なので、
- 「絵本が大好き!」
- 「絵本について幅広い知識を得たい!」
- 「絵本が好きな人たちと知り合い、一緒に勉強してみたい!」
という熱意ある方は、ぜひチャレンジしてみては?
大変な分、きっとやりがいがありますよ。
絵本専門士になれる【国立青少年教育振興機構 絵本専門士】はこちら
4 こども環境管理士
こども環境管理士とは、保育環境に自然を豊かに取り込み、保育の中に提供する専門家。
この資格は、「公益財団法人 日本生態系協会」が創設したものです。
環境大臣、文部科学大臣により環境人材認定等事業に登録されています。
子どもにとって、自然はさまざまなことを教えてくれるとても大事な存在。
たとえば、自然に関わることで、子どもたちの五感は大いに刺激されます。
そして豊かな感性、自発性、創造性、社会性が育まれます。
自然を相手にしているからこそ、感動が生まれ、思い通りにならない体験をすることも。
それを通して成長できるんですよね。
保育所保育指針でも、自然と触れ合う体験はとても重要とされています。
そして、その環境を作ることも保育士の大事な役割だとされているんです。
「自然を取り入れた保育環境を作れる保育士の能力を認めていこう」というのが、この資格のねらい。
- 「自然が大好きで、自然に関する知識を子どもたちに伝えたい」
- 「自然の中で子どもたちにより豊かな経験や発見をさせてあげたい」
と考えている保育士や、すでに実践している保育士には、ピッタリの資格ですね。
そんな、こども環境管理士の資格は、
「筆記試験(択一問題と小論文)に合格」
↓
「口述試験」
があり、それにパスすることで認証書をもらえます。
筆記試験の準備としては、「こども環境管理士講座」があります。
その教材を使って自宅で勉強すれば必要な知識が身につきますよ。
この講座は、全部で55ステップあり、1ステップは約30分で学習できる内容。
たとえば、1か月に5ステップずつ勉強していくと、1年間で修了します。
もっと短期集中で取りたい場合は、1週間に5ステップ進めると3か月で修了ですね。
とにかく、自分に合ったペースで勉強を進めていけるのはいいですよね。
今は、子どもの自然体験をウリにしている園も多いです。
自然環境が豊かな園に勤めたい保育士にも、この資格は大いに役立ちそうですね。
こども環境管理士になれる【公益財団法人 日本生態系協会 こども環境管理士】はこちら
5 幼児安全法支援員
幼児安全法支援員とは、日本赤十字社による資格。
子どもによくある事故やケガや病気への対応法と予防法を学んで取得できる資格です。
子どもの思わぬ行動から事故が起こったり、ケガをしたり。
また、何らかの病気の症状が出ることもありますよね。
そんなとき、慌てずに対処できたらいいな、と思います。
そんな、子どもたちの命や健康を守るスキルと知識を学べるのが、幼児安全法支援員の講習会です。
講習会では、まずは子どもの成長発達の過程を理解します。
そして、子どもに起こりやすい事故とその予防方法を学びます。
また、ケガの処置方法や、発熱やけいれんなどの症状への対処方法も習います。
この資格の講習は、土日に行われることが多いです。
1日(約12時間)の講習会に参加することで取得できます。
なので、割と時間が作りやすいかも。
それに、日々の保育にすぐに役に立つスキルなので、取っておいて損はないですね。
幼児安全法支援員になれる【日本赤十字社 幼児安全法支援員養成講習】はこちら
6 運動保育士
運動保育士とは、「こどもプラス株式会社」が認定している資格。
「運動遊びを通して子どもの脳や心をより健康に育むこと」をねらいにしています。
そんな運動に関する専門スキルを持った指導者を育成しているんです。
こどもプラスでは、最近の子どもは、「心と体のバランスがうまく育っていない」ことに注目。
体を動かす時間が減ってきたことで、感情のコントロールが効かなくなっているデータもあるそう。
そんな子どもたちに運動の機会や環境を与え、
「イキイキと飛び回る子どもたちの姿を取り戻し、成長を促したい」
というのが、子どもプラスの願いなんです。
確かに、昔のように自然や戸外でのびのびと体を動かして遊ぶ機会って、減っていませんか?
特に、都会の園では園庭がないところも普通にあります。
そうなると、どうしても体を思い切り動かす機会は少なくなりがちです。
それに、家に帰ればゲームやユーチューブを見て過ごすような子どもも多いと思います。
そうであれば、せめて保育園にいるときは、運動する経験をさせてあげたい。
でも、どんな運動が有効なのか、またどんな運動遊びなら子どもたちが楽しめるのか。
「運動遊びのレパートリーが広がらないな…」なんて悩んだことありませんか?
また、運動遊びは得意だけど、「体系立てて指導する知識はないな」と、行き詰っているかも。
そんな方が、運動保育士のカリキュラムに沿って学べば、
- 子どもの発達段階に合わせた運動遊びがわかる
- 子どもたちへの指導方法も習得できる
というわけです。
でも、これは子どもたちの運動の技術を上げることが目的ではないんです。
「子どもたちに運動を好きになってもらうこと」これが最も重要だとのこと。
子どもの成長を見通して、段階を踏んださまざまな運動を経験させていきます。
そして、運動を楽しみながら社会性、言語力、集中力や判断力を身につけていくんですね。
もちろん、それは決してスパルタではありません。
誰もが楽しめる運動遊びを通して、子どもの体と心をより健康にできたら、素晴らしいですよね。
運動保育士の資格は、
- 初級コース → 半日
- 中級コース → 1日(初級を取得していることが条件)
- 上級コース → 1日(中級を取得していることが条件)
の講習を受けることで取得できます。
子どもたちは、本来体を動かすことが大好き。
そんな子どもたちが目を輝かせて夢中になれる運動遊びを、あなたの保育でやってみませんか?
運動保育士になれる【こどもプラス 運動保育士資格認定】はこちら
7 幼児教育・保育英語検定(幼保英検)
幼保検定は、正式名称を幼児教育・保育英語検定と言います。
これは、一般社団法人幼児教育・保育英語検定協会が主催する検定です。
幼保英検は、幼稚園や保育園などの生活場面で使われる実用的な英語力を身につける検定試験です。
今は、一般の保育園でも英語の講師を招いて、英語の活動を行っているところがありますよね。
また、1日中英語を使って生活する保育所、いわゆるプリスクールというものも増えています。
幼い時から英語に触れさせようという動きは、今もどんどん加速しているんですね。
さらに、あなたの保育園でも外国人のお子さんが増えてませんか?
そうすると、子どもはもちろん外国人の保護者の方とやりとりする場面も出てきますよね。
でも、英語が話せなくて、「ちゃんと伝わったかな」と不安になることも多いかと思います。
そう考えると、保育士も英語力を高めておいて損はないです。
これからも、外国人の子どもを受け入れる機会は増えていきます。
そんな保育現場で、大いに役立つスキルといえますよね。
そんな保育士が英語を勉強をするときに、ピッタリなのがこの幼保英検。
幼保英検は通常の英検に比べて、子どもが日常生活で使うような英語を中心に習得していきます。
たとえば、園で英語活動を行うときに使う英語や生活の中で子どもと会話するときとか。
保護者との連絡などのやりとりに使う英語ですね。
使う場面や難易度によって段階を踏んで習得できるようになっています。
幼保英検は4級から1級まで、レベルが段階的に設けられていいます。
なので、あなたの英語レベルに合わせて受験できますよ。
「子ども(乳幼児)と会話するときの英語」なら、気軽に挑戦できるのでは?
プリスクールに転職したい場合も、資格を取得しておくと有利ですね。
幼保英検の資格が取れる【一般社団法人 幼児教育・保育英語検定協会】はこちら
8 おもちゃコンサルタント
おもちゃコンサルタントの資格は、「認定NPO法人 芸術と遊び創造協会」によって創設。
日本でただ一つの総合的なおもちゃの認定資格で、30年以上の歴史があるんですよ。
おもちゃは日々の保育には欠かせないものですよね。
市販のおもちゃを買うこともありますし、時には手作りすることも。
でも、「次にそろえるおもちゃは、どんなものがイイのかな?」と悩むこと、ありますよね。
また、保護者の方から、
「子どもにどんなおもちゃを買ってあげたらいいでしょうか」
なんて聞かれることもありますよね。
そんなとき、保護者には自信を持っておススメのおもちゃを答えたい。
園でも子どもの発達に合った楽しいおもちゃをそろえたいですよね。
そんな思いを抱いているのであれば、おもちゃコンサルタントの勉強は役に立ち
なぜなら、おもちゃの種類やそのおもちゃのねらいや与え方、遊び方を学べるからです。
「このおもちゃで子どものどんな成長が期待できるのか」といった、深い視点が生まれるでしょう。
そんなおもちゃコンサルタントの資格は、通学または、通信講座で取得できます。
通学は週に1回の全14回の講座を受けることになります。
通信講座の場合は、自分のペースに合わせて自宅で学べます。
どちらも約4か月間で受講が完了できます。
おもちゃを見る目を養えば、あなたの園にあるおもちゃの新たな魅力を発見できるかも。
子どもたちと一緒に新しい遊び方ができるかもしれませんよね。
おもちゃコンサルタントになれる【認定NPO法人 芸術と遊び創造協会 おもちゃコンサルタント】はこちら
9 保育ソーシャルワーカー
保育ソーシャルワーカーとは、子どもとその家族が幸せな生活を送るための相談支援を行う役割のこと。
保育現場でのソーシャルワークをする人、といえますね。
この資格は民間の、「日本保育ソーシャルワーク学会」が資格認定しています。
クラス担任をしていると、いろんな保護者に出会いますよね。
子育てに行き詰っていたり、家族関係に悩んでいる、とか。
たとえば、虐待や貧困やDV、うつ病を抱えている保護者の方もめずらしくないです。
「あのお母さん、大丈夫かな」なんて、気がかりに思っていても、じっくりと話を聞く時間はなかなか取れないですよね。
それに、どんな風に話を聞いてあげたらいいのか、アドバイスができるかどうかもわかりません。
そんなとき、保育ソーシャルワーカーの知識と技術が役に立ちます。
深い悩みを抱えている保護者への相談支援の方法がわかり、対応しやすくなるんです。
もちろん、保育ソーシャルワーカーを名乗って仕事ができるかどうかは、園の判断になります。
ですが、ソーシャルワークの精神を活かす、というならできます。
今までよりも客観的に保護者の気持ちを聞いて一緒に考えることができるようになります。
たとえば、「別の機関や施設につないだ方がいいのかな?」と考えられるかもしれませんよね。
保育ソーシャルワーカーになるには、日本保育ソーシャルワーク学会の研修を受ければ資格を取れます。
資格は、初級、中級、上級と段階に分かれていて、それぞれの規定の条件があります。
研修受講、修了レポートの提出などを行います。
ちなみに、初級ソーシャルワーカーの場合、
- 養成研修を2日間(1日8時間)受講
- その後修了レポートを書く
といったことが求められます。
保育ソーシャルワーカーの手法を持って、保護者対応がより適切にできるようになったらいいですよね。
保育ソーシャルワーカーになれる【日本保育ソーシャルワーク学会 日本ソーシャルワーカー】はこちら
10 認定心理士
認定心理士は、心理学の基礎的な資格です。
「公益社団法人日本心理士学会」が認定るする基礎資格となっています。
認定心理士の資格を得るには、ます、4年制大学等で心理学の基本的な知識やスキル学ぶことが必要。
その後、日本心理学会に申請することで取得できます。
これは、「4年間、心理学を専攻して基礎分野に関しては学んだ」ことの証明書みたいなもの。
高校で言えば、高校の卒業証書みたいなものなんです。
なので、認定心理士の資格だけで心理学の専門的な職業に就くことは、ちょっと難しいんですね。
でも、がっかりする必要はありません。
学んだ基礎的な心理学を活かすことで、子どもたちの内面を知ることができます。
たとえば、「この子は何でこんな行動をするんだろう」と悩むことってありますよね。
そんなときにも、心理学の観点から子どもをとらえて冷静になって考えることができます。
それって、保護者対応の場面でも使えてすごく役に立ちます。
保護者の言葉や態度を客観的にとらえられ、やりにくい保護者に対してのイライラも減ります。
なぜそんな言動で接してくるのかを一歩引いてみることができると、いろいろなことに気づけます。
それをもとに自分の接し方を調整できれば、よりよい関係づくりにつながりますよ。
ということで、残念ながら認定心理士の資格だけでその仕事に就くことは現実的ではないです。
ですが、保育士としての幅を広げてくれるスキルとして、とても相性がいい資格ですよ。
認定心理士になれる【放送大学 認定心理士】はこちら
まとめ

- 「転職を考えている」
- 「転職はまだ考えていないがスキルアップしたい」
という、どちらの人にとっても、プラスαの資格に挑戦することはメリットが大きいです。
ここで紹介したものは、どれも履歴書に書ける立派な資格。
あなたの努力と実力を社会的に証明できます。
それは単に、「自分で本を読んで勉強した」ということよりも、大きな意味を持つんですね。
社会人になっても勉強は続きます。
一生勉強と言ってもいいでしょう。
保育に活かせる新しい分野の勉強をして資格を取れれば、仕事の幅がもっと広がります。
自分の財産を増やすつもりで、ぜひ挑戦してみてくださいね。