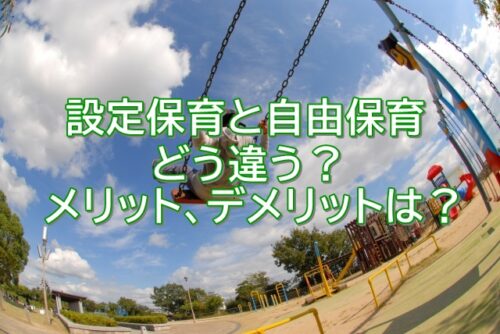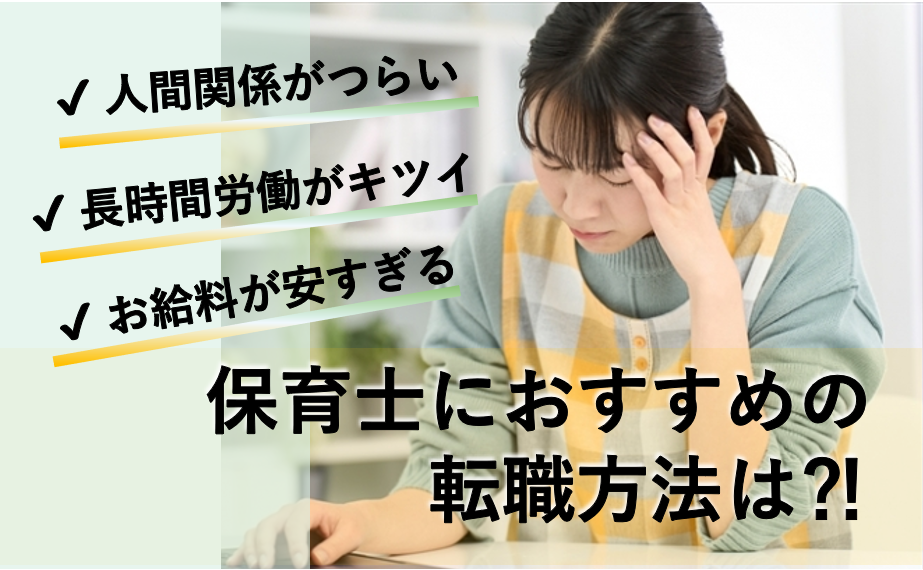こんにちは! 現役保育士はなえみです(転職でホワイト園に巡り会えました!→ プロフィールはこちら)。
保育には、「設定保育」や、「自由保育」といったやり方がありますが、あなたの園でも保育方針に基づいてスタイルを決めて取り入れていると思います。
でも、毎日保育する中で、
- 設定保育の内容を考えるのが難しい!子どもたちが興味を持ってくれない…
- 設定保育で大勢の子どもたちをまとめられない…
- 自由保育の園って、自由に遊べばいいんだから楽だよね?
なんて、設定保育や自由保育について悩んでいませんか?
この記事では、設定保育や自由保育に悩んでいる方、もっと内容をよく知りたい保育士の方に向けて、「設定保育と自由保育のそれぞれの特徴とメリットデメリット」さらに「保育する上で保育士として気をつけること」などについて解説します。
設定保育と自由保育の、それぞれの保育士の役割がよくわかるので、明日からの仕事にもきっと活かせますよ。
今まで何気なくやっていた保育を振り返ってみるきっかけになれば幸いです。
目次
設定保育と自由保育って、どこがどう違う?
そもそも、設定保育と自由保育ってどこがどう違うんでしょうか。
まず、設定保育は、「一斉保育」とも言い、「子どもたちを集めて保育士が主導で一斉に活動を行う」という保育です。
たとえば、全員で一斉に、「運動会で楽しかったことをテーマに絵を描く」「フルーツバスケットなどのゲームをする」「サーキットを設定して、みんな並んで順番に行う」といった感じですね。
これらは、子どもたちを一堂に集めて全員でする活動であり、保育士がリーダーとなって展開し、子どもたちは保育士の指示や活動の流れに沿って参加します。
一方、自由保育とは、「子ども一人ひとりが自分の好きな遊びを考えたり選んだりし、好きなように展開して好きなだけ遊ぶ」というものです。
そこに、保育士の積極的な指示や介入はなく、子どもが主体的に活動することを大切にしています。
たとえば、室内や園庭には保育士によってさまざまな遊具や遊びの素材が用意されていて、自由に取り出して思い思いに遊べるようになっています。
つまり、
- 設定保育は、「保育士が決めたテーマに沿って一斉に活動する保育」
- 自由保育は、「子どもたちが主体となって自分で好きな遊びをとことんやり込む保育」
という感じですね。
その場の保育の流れを作るのが、「保育士なのか」「子どもなのか」の違いがあるんですね。
設定保育とは
それでは、設定保育についてより詳しく解説していきますね。
設定保育とは、先ほども言ったように、子どもたちを集めて保育士が主導で一斉に活動を行う保育のことです。
設定保育は、保育士が年間の保育計画や月の計画に基づいたねらいに沿って、活動の計画を立てます。
たとえば、「3月はひな祭りがあるので、2月の後半におひなさまの製作をしよう」と考えたとします。
そうしたら、活動日までに、ひな祭りについて子どもたちにどう話すかを考えたり、製作時に使う材料を子どもの人数分準備しておいたりします。
そして、当日は子どもたちを一堂に集めてひな祭りの意味を話し、おひなさまの製作の見本を見せながら、「今日はおひなさまを作ろう」などと提案します。
そして、一通り作り方を説明し材料を配ったら、みんなで一緒におひなさまを作り始めます。
もちろん、一人ひとりの手先の使い方の状態や理解度によって、おひなさま作りの進み方は少しばらつきが出ます。
理解が早く手先が器用な子どもはどんどん作っていくでしょうが、うまくできない子には保育士が手伝ってあげながら製作を進めていき、みんなそれぞれ自分のおひなさまを完成させます。
こんな感じで、保育士が提案した活動を子どもたちが一斉に行うんですね。
このような設定保育は、多くの園で行われています。
季節の行事にちなんで製作を行ったり、集団ゲームを行ったり、運動会や発表会などの行事に向けて演目を練習したり、さまざまな形で設定保育を行っています。
設定保育で保育士が気をつけること
では、設定保育を行う上で、保育士が気をつけるべきこととは何でしょうか。
それは、
- 子どもの発達段階に沿って、興味を持てる活動を計画する
- 活動の流れを考え、必要なものを準備しておく
- 子どもに合わせて言葉を選び、わかりやすく声かけする
- 一人ひとりの様子に目を配り、必要に応じてフォローする
- みんなで取り組んだことへの達成感が持てるようにする
といった5つです。
では、詳しく解説しますね。
1 子どもの発達段階に沿って、興味が持てる活動を計画する
まずは、子どもの現在の発達段階を十分に理解した上で、興味を持って取り組めそうな活動を計画することが大切です。
たとえば、各年齢によってその時期の標準的な発達段階があり、それによってできることや楽しめることってありますよね。
ですが、発達段階に合っていない活動をしてしまうと、子どもたちは興味を持てず楽しくないので、活動にうまく乗ってくれません。
そうなると、「子どもたちがワーワーと落ち着かなくなる中で、保育士がオロオロする」といった状況にもなりかねません。
なので、子どもたちの様子をしっかりとつかんだうえで、「今のこの子たちにこんな活動を提案したら、きっと興味を持って楽しめるのでは?」と考えながら活動を計画する必要があります。
2 活動の流れを考え、必要なものを準備する
次に大事なのが、活動がスムーズに運ぶように流れを考え、活動に必要なものをキチンと準備しておくことです。
設定活動に使える時間は決まっているので、その時間内に、「導入→活動を展開→終了」までが収まるようにしなければなりません。
なので、その場の状況を見ながら活動内容を膨らませたり短くしたりできる、何らかの手立てを考えておくとスムーズです。
他にも、活動に必要な材料や道具を、数量に余裕を持って準備しておくことも大切ですね。
たとえば、思いがけなく材料を多く使ってしまうことがあると、足りなくなってしまい子どもたちの活動が止まってしまうことがあります。
その時点で慌てて足そうとしても、モノによっては難しい場合がありますからね。
そうならないように、設定保育に必要なものは数量的にもゆとりを持って準備しておきましょうね。
3 子どもに合わせて言葉を選び、わかりやすく声かけする
設定保育をする時、子どもの理解力に合わせて言葉を選び、わかりやすく声かけすることは大切です。
なぜなら、難しい言葉を使ったりわかりにくい指示を出したりすると、集中できない子が出てきて活動がまとまらなくなってしまうからです。
たとえば、みんなで一斉に折り紙を切るときに、「ここをこれぐらいの長さに切って…」などと言っても何をどれぐらいなのか、「子どもたちにはわかりにくいことがあります。
子どもってわからないことがあると、「せんせー、これでいいの?」「こうするの?」って口々に聞いてきますよね。
そうなると、一人ひとりに答えなくてはならなくなり、段々と場が騒がしくなっていって製作が進まなくなってしまいます。
それよりも、「みんなの赤ちゃん指と同じ長さに切ってね」などと言えば、子どもたちにもイメージしやすくわかりやすいですよね。
こんなふうに、子どもの理解しやすい言葉を使って指示することで、みんなが迷うことなく活動を進められますね。
4 一人ひとりの様子に目を配り、必要に応じてフォローする
設定保育を行っている間、保育士は子どもたち全体を見ながらも、一人ひとりの様子にも目を配り、必要に応じてフォローする必要があります。
なぜなら、子ども一人ひとりの発達段階には違いがあるため、一斉に同じ活動をしていても、中にはついていけない子もいるからです。
たとえば、「運動会に向けてみんなで大縄跳びをする」といった活動を行うとき、どうしても運動が苦手で大繩が飛べない子も出てきますよね。
そんなとき、その子に配慮してゆっくりとまわしてあげたり、飛べた回数に関わらず頑張っていることをほめてあげたりすることだ大切です。
あるいは、その子が自分のペースで大繩の練習ができるように別の時間を作って、保育士がつきあってあげることもいいかもしれませんね。
このように、設定保育をする時には、ついていけない子や戸惑っている子がいないか、しっかりと目を配ってその子を何らかの形でケアしてあげることが大切ですね。
5 みんなで取り組んだことへの達成感が持てるようにする
設定保育の活動の最後には、みんなで一緒に取り組んがことへの達成感が持てるような声かけをしましょう。
そうでないと、子どもたちは自分の成果だけに注目して終わってしまい、それではみんなで一緒に活動したことの意味が薄れてしまいます。
たとえば、みんなでリレーをしたら、勝ち負けの結果だけでなく、「走るのが早くなったね」「順番を守って走れたね」「お友だちのことを応援してあげていたね」など、活動の中でよかったことをしっかりと伝えてあげます。
そうすると、子どもたちも友だちの行動に気づいて、「うれしいな」「すごいな」「自分も今度はやってみよう」と思えますよね。
そして、みんなで一緒にリレーをやった達成感を感じられ、「またやりたい」と思えるんですよね。
なので、設定保育の最後には、子どもたち自身が、「みんなでやって楽しかった!」と思えるように、子どもたちの頑張ったところやよかったところを伝えてあげましょう。
設定保育を行うメリット、デメリット
さあ、設定保育についていろいろと解説してきましたが、ここでは、設定保育を行うメリット、デメリットを改めて整理したいと思います。
設定保育のメリット
まずは、設定保育のメリットですね。それは以下のようなことがあると思います。
- 保育士一人でも、全員を把握しながら保育が進められる、
- 子どもの見る力、聞く力を身につけられる
- 友だちと一緒に取り組みやり遂げる楽しさが味わえる
- 新しい遊びに興味を持ちやってみるきっかけになる
- 勝ち負けなどのゲームが楽しめて、そこで気持ちのコントロールを学べる
- 課題の達成度合いで子どもの発達の様子を測れる
- 保護者には、子どもの成長した姿や成果が見えやすい
ですね。
まず、設定保育は、子どもたちを一堂に集めて一斉に同じ活動をするので、確かに全体を把握しやすいですよね。
また、子どもたちはリーダーである保育士の話をきちんと聞き取って行動する必要があるため、「見る力」「聞く力」が育ちます。
そして、設定保育の流れに乗ることで、子ども自身あまり興味がなかった活動を経験するきっかけになります。
「やってみたら意外と楽しかった」というような経験も貴重なものになるはずです。
たとえば、設定保育でよくあるのが、集団ゲームですが、それもまずはみんなで行うことで、「こんなゲームがあるんだよ」ということを知らせることができます。
その後は、そのゲームを気に入った子どもたちだけが集まってゲームを再現することが多いですが、ルールを守ることや勝ち負けを経験することによって、気持ちをコントロールすることを学べます。
また、一斉に同じ設定保育をすることで、一人ひとりの子どもの発達の様子がわかりやすいです。
たとえば、ドッジボールをしたとして、
- ○○ちゃんは、「ボールをよく見ていて、どこにいれば当たらないかを考えながら体を動かしている」
ということがわかり、その一方で、
- △△ちゃんは、「ボールから目が離れやすく、意識がそれやすいため当てられてしまうことが多い」
といったようなことが見えてきます。
もちろん、「できる」「できない」だけで子どもを見るわけではないですが、設定保育をすることで子どもたちそれぞれの発達の様子が見えやすいということはあるかと思います。
さらに、保護者の方には、「設定保育の様子を見てもらうことで、わが子の成長を実感してもらえる」といったことがあります。
たとえば、「みんなと一緒に座って先生の話を聞いている」とか、「体操やダンスをみんなと一緒にしている」などという姿を見ると、「わが子もこんなことができるようになったんだな」とうれしく思うんですよね。
ただ、保育士としては、「できた」「できてない」といったことだけに注目してほしくはないんですが、そこは担任が、その子の別の良いところや頑張っていることを伝えられたらいいのかな、と思います。
設定保育のデメリット
それでは、設定保育のデメリットとは何でしょうか。
それは、
- 一人ひとりの発達状況に合わせることができない
- 好きな遊びをトコトンできない
- 受け身になりがち
といったことでしょうね。
つまり、先ほどのメリットの裏返しといったことですね。
まずは、設定保育は一斉にみんなで一つの活動に取り組むので、どうしても一人ひとりに合わせることは難しいです。
そうすると、理解できない子やついていけない子が出てくることがあり、そんな場合は、保育士のフォローが必要になりますよね。
そして、設定保育をする分、子どもたちは好きな遊びがトコトンできないことになります。
たとえば、保育士が、「さあ、今日はリトミックやるよ~。そろそろお片付けして~」なんて声をかけるので、そうすると子どもたちは好きな遊びを中断させられることになりますよね。
そして、設定保育が習慣になっていることで、「遊びや生活で受け身になりがち」ということがあります。
思えば、私が保育園で5歳児を担任していた時も、子どもたちは登園してくると、「せんせー、今日は何するのー?」と聞いてきましたね。
これまで私は、そのことを特に変だとは思っていなかったのですが、自由保育の園の子どもたちは朝登園してくると、「今日は、○○して遊ぶ!」と言うそうです。
それをきいて、「なるほど!」と思ってしまいました。
私は、「子どもたちは毎日楽しみに保育園に来てくれているんだな~」なんて思っていたんですが、受け身と言われれば、残念ながらそうなのかもしれませんね。
自由保育とは
それでは、自由保育について解説していきましょう。
自由保育とは、「子ども一人ひとりが自分の好きな遊びを考えたり選んだりし、好きなように展開して遊ぶ」といった保育で、いわゆる、「子どもの主体的な遊び」を尊重する保育スタイルです。
園によっては、年齢別のクラス保育ではなく、異年齢が混合になっての自由保育を行っている園もあります。
たとえば、室内や廊下では、ブロック、製作、お絵かき、ままごと、レール汽車などで好きな友だちと好きなように遊びます。
また、園庭では、滑り台や木登り、虫探し、鬼ごっこ、リレー、砂遊び、三輪車に乗るなど、これも好きな遊びを好きなだけトコトン楽しみます。
もちろん、自由だからと言って何をしても許されるということではありません。
危険なことや、友だちを傷つけることはしてはいけませんし、時間だって無限というわけにはいきません。
遊びのルールを守ったり、相手を思いやって譲ることや順番を待つことも大切です。
なので、保育士は、あらゆることを常に予測しながら、きちんと助言したり助け舟が出せるように、それぞれの遊びに目配りし子どもたちの様子を把握します。
また、引っ込み思案で自分から遊べない子には、遊びの提案をしたり誘ったりして、遊びを見つけられるように寄り添います。
もちろん、自由保育でも自由な遊びを通して達成したい保育のねらいがあるので、それもとにした遊びの環境設定を考えます。
たとえば、子どもが興味を持ちそうな玩具を置いておく、必要な材料を補充しておく、提案できそうな遊びを考えておく、といったことですね。
子どもたちに、「こんな経験をしてほしい」という思いと、「実際の子どもたちの興味」の両方を考えて、保育前の下準備をしています。
つまり、自由保育には保育士の意図も密かに忍ばせながら、子どもの自由な遊びをサポートするために、細かな配慮や準備が必要になるんですね。
自由保育で保育士が気をつけること
では、自由保育で保育士が気をつけるべきこととは、どんなことでしょうか。
それは、
- 一人ひとりの遊びや行動を把握する
- タイミングを見て声をかけ遊びのサポートをする
- 指示はせず、子どもに考えさせ選ばせる
- 保育のねらいを入れ込んだ環境設定をする
といったものです。
では、一つずつ見ていきましょう。
1 一人ひとりの遊びや行動を把握する
自由保育は、子どもたちが好きなところで好きな遊びをするので、広い範囲に散らばっている感じになりますが、キチンと一人ひとりの遊びや行動を把握する必要があります。
なぜなら、自由保育は放任ではなく、保育士がしっかりと子どもの遊びを見守りながら、必要に応じて適切な助言をしたり友だちとの仲立ちなったりする必要があるからです。
また、どこで誰が何をしているかを把握していなければ、もし事故によるケガなどがあったとしても、園長にも保護者にも状況説明ができません。
「すみません、(事故を)見ていませんでした…」では通用しませんからね。
なので、子どもたちが広範囲で遊ぶ自由保育で、子どもたちに目を行き届かせることは、保育士としては結構大変ですが、とても重要なことなんです。
2 タイミングを見て声をかけ遊びのサポートをする
自由保育では、保育士が積極的に遊びを引っ張ることはしないですが、ちゃんとタイミングを見て子どもに声をかけたり、必要に応じて遊びのサポートをします。
もちろん、遊びが盛り上がってれば、見守っていればいいかもしれません。
ですが、ちょっとしたアイデアを提案してみることで、遊びがもっと楽しくなるかもしれませんよね。
ただ、ここのタイミングの測り方や何を提案するのかは結構難しく、大人が介入したことで、子どもたちの主体的な遊びではなくなってしまうことがあります。
なので、ここは保育士の経験と腕の見せどころとなりますね。
3 指示はせず、子どもに考えさせ選ばせる
自由保育では、保育士が子どもたちに遊びの指示をするのではなく、子ども自身に考えさせ選ばせるようにします。
たとえば、やりたい遊びが見つからない子や、仲間に入っていけない子がいたら、その子の気持ちに寄り添いながら、遊びの選択肢を示してみたり、遊びに入っていく後押しをしてあげたりします。
また、「友だち同士でもめているな…」と気づいたときも、すぐに保育士が割って入るようなことはしません。
「ダメでしょ」「こうしなさい」と指示するのではなく、子ども同士のやりとりを見守ってから声をかけ、「どうしたらお互いの気持ちが分かり合えるかあえるか」を、子ども自身に考えさせ解決に導きます。
こういった、子どもを見守り待つこと、自分たちで考えられるように導いていくのには、かなりの高度な保育スキルが必要で、頭ではわかっていてもなかなか難しいですよね。
このように、保育士は陰ながら子どもを見守りつつも、その場面に合った声かけをし、子ども自身が考えて選び行動できるようにサポートしなければならないんですね。
4 保育のねらいを意識した環境設定をする
自由保育でも、保育士のねらいはあります。なので、そのねらいを意識した関わりを心がけ、環境設定をする必要があります。
たとえば、「順番や簡単なルールを守りながら友だちと遊ぶ」というねらいがあったら、友だち同士でもめている場面を通じて、「順番で使う」ということをさりげなく知らせます。
それは、保育士が「順番で使いなさい」と指示するのではなく、子どもたちが気付けるように知らせていくことが大切なんです。
また、「さまざまな材料で工夫して作る」というねらいがあったら、空き箱などの廃材を用意しておいて、「子どもたちの作りたい、工夫してみたい」という気持ちを誘うようにしておきます。
このように、自由保育は、ただ漠然と子どもに好きな遊びをさせて放置するのではなく、ちゃんと保育のねらいに基づいた関わりや環境設定をしているんです。
自由保育のメリット、デメリット
ここからは、自由保育のメリットデメリットについて解説します。まず、自由保育のメリットは以下のようになります。
自由保育のメリット
- 子どもたちに主体性や自発性が身につく
- 好きな遊びに集中でき満足感が得られる
- 自分で考えて工夫したり解決する力が身につく
- 友だちとのコミュニケーション能力が育つ
自由保育では、子どもがしたい遊びを自分で選べるので、主体性や自発性が身につきます。
また、設定保育の時間がない分、自分で選んだ好きな遊びにじっくりと集中できるので、満足感も得られます。
そして、自分で選んだ遊びを工夫したり、もっと楽しくできないか考えたりすることで、思考力も鍛えられます。
もし、何か問題が起こった時にも、保育士が解決してくれるのではなく、自分たちで考えるようなヒントを与えてもらうので、自分で解決する力も身につきます。
さらに、自由保育だからと言って、何でも自分の思い通りになるわけではありません。
もめた時には、自分の気持ちをちゃんと言葉で友だちに伝え、友だちの気持ちも理解して折り合いをつけていかなければなりません。
もちろん、必要に応じて保育士が間に入ることもしますが、基本は自分たちで考えて解決するように促していくので、友だちとのコミュニケーション能力が身につきます。
なので、自由保育だから自分勝手になるとか、わがままになる、ということではないんですよね。
自由保育のデメリット
それでは、自由保育のデメリットについて以下に挙げていきますね。
- 保育士の人手が必要
- ある程度広い保育環境が必要
- 保育士の経験と力量が問われる
- 放任になってしまっている園がある
- 保護者から、「ただ遊んでいるだけ」と思われてしまう
- 小学校に上がってから適応できるか心配
自由保育では、保育士が子どもたちのことをしっかり把握するとなると、どうしても人手が必要になるんですよね。
なせなら、子どもが自由に遊びを選ぶということは、遊ぶ場所もある程度の広さがないと成り立ちませんよね。
そんな広い場所に散らばって遊んでいる子どもたちの状況を細かく見るとなると、やっぱり人手が必要になってしまうんです。
それに、そんな環境の中でも子どもたちを見守り、絶妙なタイミングで声をかけたり、ねらいに沿った関わりをするのですから、保育士には相当な保育経験や力量が求められます。
なので、「自由に遊ばせておけばいいんだから、自由保育って楽だよね」なんていうのは、全く違うんですよね。
ですが、残念なことにそう思っている保育士も中にはいて、キチンと子どもを把握していなかったり、環境設定ができていなかったりする園もあるんです。
また、保護者に自由保育について正しく理解してもらっていないと、、「ただ遊んでいるだけ」「何も指導してもらっていない」なんて思われてしまいます。
特に、年長さんの保護者の中には、「自由保育だけだと、小学校に行ってから困るのでは?授業をちゃんと聞けるのかしら?」と不安に思う方がいます。
そういう場合は、自由保育の意味や保育のねらい、保育士がどんな関わり方をしているのかをしっかりと説明して、自由保育でも子どもにとって必要な力を伸ばせることを伝える必要がありますね。
園の方針によって保育の取り組みはさまざま
設定保育と自由保育について、理解していただけましたでしょうか。
「設定保育を行うのか」「自由保育を取り入れるのか」は、園の保育方針によってさまざまですが、よくあるのは、「設定保育+自由保育」という混合パターンでしょう。
もちろん、信念を持って、「ウチは自由保育をメインにしています!」という園もあります。
ただ、そんな自由保育の園のホームページをいくつか見てみると、「設定保育は全くしない」ということでもないようですね。
運動会や発表会、遠足などの行事があったり、みんなで一斉に紙芝居を見たり歌を歌ったりしている様子も見られるので、必要に応じて設定保育を行っているようですね。
そもそも、自由保育を掲げている園は少ないですね。
都心の園舎や園庭は狭いところが多く、広い園もありますが、広すぎても自由に遊ぶ子どもたちに目を行き届かせることが難しいです。
そのためには保育士の人数を増やさなくてはならないからです。
そういった、環境面や人材の面からも自由保育を実現させるのはなかなか難しいのかもしれませんね。
設定保育でも自由保育でも子どもを伸ばせる!
このように、設定保育と自由保育にはメリット、デメリットがありますが、どちらの保育もちゃんと子どもの力を伸ばせることがわかりますね。
もちろん、それには保育士の経験や力量が大きく関わってきます。
どちらの保育をするにしても、保育士が子どもの遊びの専門家として、高い意識を持って保育に当たれば大丈夫なんですね。
設定保育の中でも、子どもの興味や主体性を引き出す関わりは工夫できるはずですし、自由保育の中でも、ルールや規律を伝え、見る力や聞く力を育てられます。
なので、「設定保育はダメで、自由保育がイイ」とか、その逆も決めつけることはできないんですね。
子どもの力を伸ばせるカギは、保育士であるあなたが握っているんですよ。
まとめ

設定保育も自由保育も、それぞれにメリットデメリットはありますが、どちらの保育でもちゃんと子どもの力を伸ばせます。
いずれにしても、保育士が子どもの遊びの専門家として、高い意識を持って保育に当たることが大切なんですよね。
もし、あなたが自由保育に興味があれば、自由保育をメインカラーとしている園で働いてみるのもいいですね。
新しい経験を積めば、保育士としてのキャリアの幅も広がりますよ。
逆に、「今いる園が自由保育の園なんだけど、自分の思っている保育とは違う」という方もいるでしょう。
それが、時には精神的な苦痛になってしまうこともあるんですよね。
なので、その場合は無理はしないで、違う形の保育をしている園を探してみるのもいいと思います。
保育士転職サイトであれば、各園の保育の特徴がわかるので、どんな保育をしている園なのか教えてもらったうえで、求人に応募できますよ。
これまで経験してきた保育スキルを糧にして、あなたのやりたい保育ができる園で働けるよう、ぜひ動き出してみてくださいね。