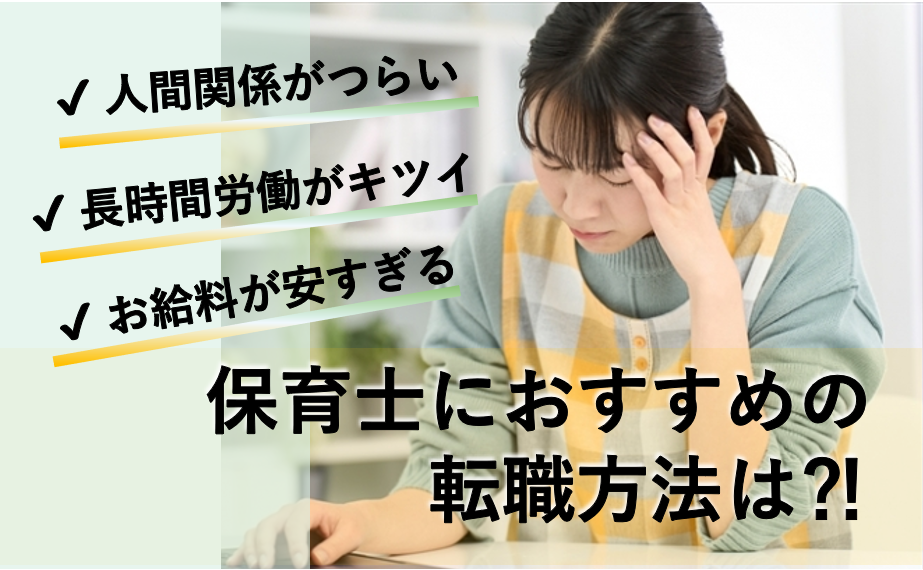こんにちは! 現役保育士はなえみです(転職でホワイト園に巡り会えました!→ プロフィールはこちら)。
保育士の方が転職を考える時、次の職場としてあがりやすい人気の園は、「小規模保育園」なんですよね。
小規模保育園は、少人数の乳児を預かる保育園であり、そのイメージから、
- 「乳児相手だし、ゆったりしていそう」
- 「アットホームに働けそう」
なんて思いますよね。
でも、転職するなら、いいところも悪いところもキチンと知っておいた方がいいですね。
この記事では、小規模保育園への転職を考えている保育士の方に向けて、「小規模保育園の認可基準と特徴」そして、「保育士が小規模保育園に転職するときのメリット、デメリット」について解説します。
この記事を読めば、小規模保育園の成り立ちからよくわかるので、あなたに小規模保育園が合っているのかも見えてきますよ。
その上で、効率よく転職活動を進めていってくださいね。
目次
小規模保育園とは
小規模保育園とは、「0歳児~2歳児までの子ども、6~19人を預かる保育施設」のことを指し、これまでは認可外保育園に含まれていた施設なんです。
ですが、2015年の子ども・子育て支援新制度によって、「地域型保育事業」の中の「小規模保育事業」に位置づけられ、認可保育園になりました。
もちろん、認可園になるには、国による一定の基準を満たす必要があります。
そして、認可されることによって、「施設運営費として公的な補助金が受けられる」という点で大きく変わるんですね。
ただ、認可基準を満たしていても、すべての小規模保育園が認可を申請するわけではなく、「あえて認可外保育園のままでいこう」という小規模保育園もあるんです。
なぜなら、認可外保育園として運営していった方が、市区町村からの関与を受けずに、事業者なりの独自のサービスを自由に展開できるからなんです。
ちなみに、小規模保育園を認可するのは市区町村で、その後の園の指導監督も行います。小規模認可保育園の事業主体は、市区町村や民間事業者などになります。
小規模認可保育園の基準
それでは、小規模認可保育園の基準についてみていきましょう。
小規模認可保育園は、国が定めた基準に沿って市区町村が作った設置基準をクリアしているんですよね。
国は、小規模保育事業をA型(認可保育所の分園型)、B型(A型とC型の中間型)、C型(保育ママのグループ型)の3つに分けています。
この3種類の小規模認可保育園について、それぞれの基準を下記にまとめてみました。
| A型 【認可保育園分園型】 |
B型 【AとCの中間型】 |
C型 【保育ママのグループ型】 |
|
| 定員 | 6~19名 | 6~19名 | 6~10名 |
| 保育士有資格者 | 全員が保育士(保健師または、看護師1名を保育士としてもよい) | 半数が保育士(保健師または、看護師1名を保育士としてもよい) 保育士以外には研修を実施する |
家庭的保育者(研修を修了した保育士、保育士と同等以上と区市町村長が認める者) |
| 職員数 | 0歳児→3:1 1、 2歳児→6:1 さらにプラス1名 |
0歳児→3:1 1、 2歳児→6:1 さらにプラス1名 |
0~2歳児→3:1 (補助者を置く場合は5:2) |
| 保育室 | 0、1歳児は乳児室、ま たはほふく室3.3㎡/人 2歳児は保育室1.98㎡/人 |
0、1歳児は乳児室、ま たはほふく室3.3㎡/人 2歳児は保育室1.98㎡/人 |
0~2歳児3.3㎡/人 |
| 屋外遊技場 | 2歳児3.3㎡/人(付近の代替え地でも可) | 2歳児3.3㎡/人(付近の代替え地でも可) | 同一敷地内に遊技場等に適当な広さの庭(付近の代替え地でも可) |
うまり、上の表を簡単にまとめると、
- A型とB型では、保育士の割合が違うだけ( A型は全員が保育士、B型は半数が保育士)で、他の基準は同じ
- C型は、A型とB型よりも子どもの人数が少なく、保育士でなくてもOK、環境の基準も緩い
となります。
特に注目すべきなのは、保育士有資格者の割合が、「A型>B型>C型」といった順に少なくなっている点ですね。
つまり、保育士資格を持っている人が少なくても、園を運営できるようにしているわけです。
たとえば、「都会で敷地がない」「保育士がなかなか採用できない」など、園を作りにくい条件にあっても、小規模保育園なら開設しやすいということなんですね。
ですが、「保育士有資格者が少なくて、保育の質が保たれるのか?」と考えると、ちょっと心配かもしれませんね。
認可外の小規模保育園が認可されるとどう変わるのか?
認可外の小規模保育園が認可されると、以下のような4つの点で変化があります。
- 国が定めた基準に沿った施設設置、職員配置が必要となる
- 園の運営費に対する補助金が受けられる
- 入園の申し込み受付や保育認定は、市区町村が行う
- 保育料は保護者の応能負担となる
では、一つずつ具体的に説明しますね。
国が定めた基準に沿った施設設置、職員配置が必要となる
小規模保育園が認可されるためには、国が定めた基準に沿った、市区町村による設置基準を守らなければなりません。
この基準は、認可外保育園の基準に比べて高いものになっていて、たとえば、保育室面積や保育士有資格者の割合などは、高めの基準となっているんです。
園の運営費に対する補助金が受けられる
小規模保育園が認可されると、園の運営費に対する補助金を受けることができるんです。
市区町村によって金額は異なりますが、平均で年間3,500万円程度が受けられるんですよ。
そのため、園は資金がうるおうので、安定的な運営ができますよね。
入園の申し込み受付や保育認定は、市区町村で行う
小規模認可保育園の入園の申し込みは、市区町村が窓口になります。
そして入園児選考も、市区町村が保育の必要性が高い子どもから順番に保育認定をし、調整しながら入園児を選考します。
このように、市区町村が入園希望者を広く受け付け、定員の空きがある園に振り分けるので、園はそれほど苦労せずに入園児を獲得できるんですね。
一方、認可外の小規模保育園の場合は、市区町村をはさまず、保護者が直接園に行って事業主と契約し入園できるようになっています。
保育料は保護者の応能負担となる
小規模認可保育園の保護者が負担する保育料は、応能負担となっています。
応能負担とは、「保護者の収入額に応じた保育料を払ってもらう」というものです。
なので、収入が低い保護者が払う保育料は、収入が高い保護者が払う保育料に比べて、安くなるんですよ。
小規模認可保育園には補助金が下りて、それを主な財源にできるため、応能負担でも経営的には大丈夫なんですね。
ちなみに、認可外の小規模保育園の場合、補助金はなく、園の財源は保護者からの保育料がすべてです。
そのため、保護者の収入額に関係なく保育料は全員が高額になってしまうんですね。
以上のように、小規模認可保育園は認可外のときに比べて制約が多くなりますが、「補助金が受けられ、市区町村が入園児を調整してくれるため、安定した運営ができる」というところがメリットなんですね。
国が小規模保育園を認可する狙いとは?
では、国は小規模保育園を認可事業とすることで、何を狙っているんでしょうか。
一つ目は、「待機児童の解消」です。
待機児童は0~2歳児までの子どもが中心です。
なので、0~5歳児までの大型の保育園でなくても、0~2歳児までの小規模保育園をたくさん作ることができれば、待機児童解消につながりますよね。
たとえば、小規模保育園であればビルの一部など、大都市の狭い場所でも作りやすく、期間も4~5か月ほどで作ることができます。
短期間で設置でき、補助金によって安定した運営ができる認可の小規模保育園ならば、開設に乗り出す事業者が増えるかもしれませんよね。
ただ、小規模保育園に入園後、「3歳児に進級したらどうしたらいいの?」という疑問がわきますよね。
実は、小規模認可保育園の子どもが卒園したとき(3歳児以降)には、「認定こども園」「幼稚園」「保育園」などの連携施設に優先的に入園できることになっているんです。
そうでないと、保護者は子どもが3歳児になる前に、ふたたび保育園を探す、いわゆる、「保活」で苦労することになってしまいますからね。
それは、100%保障するとまではいかないんですが、「3歳児以降の保育の受け皿(園)の確保」は、認可の条件に含まれてはいて、そうすることで保護者の不安を取り除こうとしているんですね。
二つ目は、「地方の子育て機能を守る」ということです。
人口が減る傾向にある地方では、子どもの減少によって、「地域の保育園が廃園になる」という問題が起きているんです。
そんな地方でも、小規模認可保育園なら、地域の実情に合わせた形態を選んで作りやすいので保育園が存続できます。
また、補助金がもらえるので、廃園のリスクも減らせますよね。
その結果、地域の子育て環境を守ることができるんです。
このように、小規模認可保育園は、都市部と地方が抱える子育ての問題を解決する役割を担っているんですね。
小規模保育園の保育
では、小規模保育園の保育の様子を簡単に紹介しますね。
小規模保育園のクラス分けは、一般の認可保育園のように年齢別で保育する園と、「0歳児と1歳児の低月齢児を一緒にする」「1歳児の高月齢児と2歳児を一緒にする」など、異年齢児を混合で保育する園があります。
保育は、年間指導計画、月案、週案などをきちんと作成し、それに沿って行われます。
活動自体は、一般の認可保育園の0~2歳児の内容と同じものになりますね。
登園から降園までの1日の生活の流れも、大きく変わらないです。
そして、運動会、発表会、季節ごとの行事なども行います。
ただ、幼児がいないため行事の規模は小さく簡単なものになりやすいですね。
そもそも、0~2歳児は高度なことはできないので、運動会や発表会に参加するといっても、「毎日必死に練習する」なんてことは必要ないですよね。
なので、保育士も気を楽にして取り組めます。
小規模保育園の5つの特徴
続いて、「小規模保育園の5つの特徴」について見ていきましょう。
それは以下の通りです。
- 一人ひとりに丁寧できめ細やかな対応ができる
- 乳児ならではの保育力が求められる
- 乳児の生活に関する保育が中心となる
- 一斉活動よりも、自由遊びの見守りが中心となる
- 噛みつきや、ひっかきなどのトラブルが起こりやすい
一人ひとりに丁寧できめ細やかな対応ができる
小規模保育園は小規模なので、一人ひとりの子どもに丁寧にきめ細やかな対応ができます。
たとえば、認可の小規模保育園のA型とB型には、一般の認可保育園と同じ基準の職員数に1名多く配置することが決まっていますよね。
C型の場合は、保育士ではなく家庭的保育者になりますが、「0~2歳児3人:職員1人」と手厚い配置になっています。
これなら、一人一人にきめ細やかに関われます。
ちなみに、私が勤めていた一般の認可保育園では、「0歳児6人:保育士2人」「1歳児15人:保育士3人」「2歳児18人:保育士3人」で子どもを見ていました。
認可基準は満たしていますが、保育をしていても、決して余裕がある状態ではありませんでしたね。
一人でも保育士が休むと、主任か幼児組の保育士に応援に入ってもらわないと、キツイ状態でした。
それに比べると、認可の小規模保育園は職員配置にゆとりがあって、一人ひとりの子どもにゆったりと関わり、ていねいな保育ができますよね。
乳児ならではの保育力が求められる
小規模保育園では、0~2歳児の乳児ならではの保育の力量が問われます。
発達の個人差が大きいこの年代の子どもの保育には、その年齢や月齢ごとの発達を理解した上での関わりが必要だからです。
たとえば、0歳児は月齢が1ヵ月違えば、子どもの成長、発達の様子はかなり違ってきますよね。
なので、保育士は子どもの発達の状態を細やかに見極め、さらに個性なども把握したうえで一人ひとりに合わせた保育や支援をする必要があるんです。
また、2歳児は反抗期に入ってきますが、保育士はそれを、「わがまま」ではなく、「自我の芽生え」と肯定的に受け止めてあげることが大切ですよね。
ここできちんと子どもの意思を受け止め、あるいはちょっと気をそらしてあげることで、子ども自身が満足できます。
そんな乳児の特徴を知った上で、キチンと子どもに対応する力が求められるんですよね。
乳児の生活に関する保育が中心となる
小規模保育園では、乳児の生活に関することが保育の中心になります。
0~2歳児は、食事や着脱、排せつなどの生活動作に対して介助してもらう割合が多く、しかも一人ひとりに丁寧に関わってあげる必要があります。
子どもが意欲を持って、食事や着脱や排せつができるように、保育士は加減をしながら介助していきます。
保育士にとって、こういった保育は毎日同じことの繰り返しなので単調になりがちですが、子どもの成長発達には欠かせない大事な支援なんです。
保育士は、個々の子どものできることを増やすために、温かな言葉かけとまなざしを持って、根気よく働きかけて成長を促していきます。
一斉活動よりも、自由遊びが中心となる
小規模保育園では、一斉活動よりも自由遊びが忠心になります。
なぜなら、0~2歳児にとって、3~5歳児のような一斉活動(製作やゲーム遊びなど)は、難しいですからね。
なので、屋外ならば公園に出かけて、子どもが自由に遊具で遊ぶ様子を見守って介助したり、一緒に追いかけっこをして遊んだりします。
また、室内ならば、ままごとや汽車、積み木、パズルなど子どもが好きな遊びを楽しめるように環境を整え、子どもたちが自分の遊びをトコトン楽しめるようにします。
もちろん、自由遊びだからといって放任というわけではなく、一人ひとりの子どもが好きな遊びを十分に楽しみ、さらに発展するように工夫したり関わったりすることが、保育士の大事な役目なんですよね。
噛みつきや、ひっかきなどのトラブルが起こりやすい
1、2歳児は、自分の気持ちを言葉で表現できないため、噛みつきやひっかきをすることが多いですよね。
なので、保育士はそれを未然に防ぐよう、常に注意深く子どもの様子を見守らなくてはなりません。
噛みつきやひっかきは、特定の子どもが起こすことが多く、また同じ子どもが繰り返し噛まれることがありますよね。
そうなってしまうと、保護者から不信感を買うことになりますし、さらに保護者同士のトラブルに発展する場合もあるんです。
私が担任していたクラスにも、噛みつきをする子がいて、それもいつも特定の子を噛んでしまうので、毎日目が離せない状態でした。
どんなに注意していても、ふとした瞬間に噛みついてしまうので、本当に気が休まらなかったことを覚えています。
そして、保護者同士の不信感が募ったあげくに、「噛みつきをする子どもの保護者がいたたまれずに、転園することになってしまった」という苦い思い出があります。
もちろん、こういったことは小規模認可保育園に限らず、0~2歳児クラスであればどこでも起こりうることです。
そんな悲しい結果を避けるためにも、保育士は、常に子どもの行動の予測をしながら保育することが求められます。
また、なぜ噛みつきが起こるのかその背景を考え、職員同士で連携して対策を取り、保育することがとても大切ですよね。
小規模保育園に転職する8つのメリット
ここからは、「保育士が小規模保育園に転職する8つのメリット」について解説します。
- 給料が高い可能性がある
- 保育設備や玩具などがそろいやすい
- 認可外保育園や認証保育園に比べて、保育室が広い
- 一人ひとりの子どもに丁寧に向き合い、自由な保育ができる
- すべての子どもを職員全体で把握しており、保護者との信頼関係を作りやすい
- 体力や気力に余裕を持って保育できる
- 大がかりな行事が少なく、残業や持ち帰り仕事も少ない
- 少人数の職員同士で連帯感を持って働ける
給料が高い可能性がある
認可の小規模保育園の保育士の給料は、高い場合も多いです。
なぜなら、認可の小規模保育園は市区町村からの補助金を受けられるので、その分経営が安定し運営費にゆとりがあるからです。
経営が安定し、資金にゆとりがあれば、保育士の給料は保障されやすいですからね。
実際に求人を見てみると、園によって18万円~22万円くらいの幅があります。
高給とはいきませんが、比較的仕事の負担が少ない小規模認可保育園であれば、よい給料といえますね。
保育設備や玩具などがそろいやすい
認可の小規模保育園の設備や玩具は、いろいろなものがそろいやすく保育しやすいです。
上にも述べたように、認可の小規模保育園には補助金が下りるため、運営費全般にゆとりが生まれます。
そうすると、保育のための備品や玩具の予算を取りやすく、購入しやすいですよね。
保育の備品や玩具などが充実すると、保育士はより良い環境で仕事ができますよね。
認可外保育園や認証保育園に比べて、保育室が広い
認可の小規模保育園は、認可外や認証などの保育園と比べて保育室が広い傾向にあります。
認可の小規模保育園の保育室基準(3.3㎡/人)は、認可外保育園(1.65㎡/人)や認証保育園(2.5㎡/人)に比べて広めの基準になっているんですよね。
なので、乳児保育が希望で、なおかつ保育環境を重視したい方は、認可の小規模保育園を選ぶとよいですね。
一人ひとりの子どもに丁寧に向き合い、自由な保育ができる
小規模保育園は、一人ひとりの子どもに丁寧に関わり、自由な保育がしやすいです。
先ほど話したように、比較的手厚い職員数で保育していますし、子どもたちは少人数なので、子どもの体調や天気などに合わせて、活動を柔軟に変更できます。
こんなふうに、比較的自由に、無理なく保育を展開できるところは魅力ですよね。
すべての子どものことがわかり、保護者との信頼関係を作りやすい
小規模保育園の職員は、全員が子ども一人ひとりの顔と名前を把握しています。
園には、多くても19人程度の子どもたちしかいませんからね。
そうすると、職員同士でも打ち合わせをしたり子どもの話をしたりするときに、意思疎通がしやすく、保育の連携をとりやすいんです。
さらに、保護者との距離も近くなり、信頼関係が作りやすいのもメリットですね。
「どの先生も、自分の子どものことを知っている」ということは、保護者にとってはとてもうれしく、安心なことなんですよね。
それが、園への信頼感につながり、保育士は保護者とより良い関係が築けるんです。
体力や気力に余裕を持って保育できる
小規模保育園では、保育士は体力や気力に余裕を持って保育できます。
なぜなら、0~2歳児の乳児なら動きはゆっくりで、遊び方も小ぢんまりしているからです。
また、心の発達が未分化で、3~5歳児のように情緒的なことが原因で問題行動が起こることは少ないので、対応に悩む場面も少ないです。
そのため、体力や気力をひどく消耗することなく働けるんですね。
大がかりな行事が少なく、残業や持ち帰り仕事も少ない
小規模保育園では、大がかりな行事が少ないので、残業や持ち帰り仕事も少ないです。
もちろん、行事はありますが、参加するのは乳児でしかも少人数なので、それほど大々的なものではないんですよね。
また、園によっては行事自体が少なく、「あっても季節ごとの簡単な行事のみ」という場合があります。
そうすると、そのための衣装や小道具づくりなどが必要ないので、必然的に残業や持ち帰り仕事も少なくなりますよね。
ただ、行事の数や規模は園ごとによって違うので、確認が必要ですね。
ほかにも、子どもたちに製作をさせるための材料の下準備をするときにも、子どもが少ないので、用意する物は少なく、短い時間で準備できますよね。
少人数の職員同士でアットホームに働ける
小規模保育園の職員数はおよそ10名前後なので、アットホームな雰囲気の中で働けます。
一般的な保育園に比べると、職員数がずっと少ないんですよね。
なので、どの職員とも毎日のように接する機会があり、意思疎通がしやすく連帯感を持って仕事ができるでしょう。
「アットホームな職場で働きたいな」という人には向いていますね。
小規模保育園に転職する6つのデメリット
では、「小規模保育園に転職するときのデメリット」を6つ解説していきますね。
- 集団保育のスキルが身につきにくい
- 園庭や広いホールがなく、公園に行くことが多い
- 人手不足の場合、一人の仕事が多く休みを取りにくい
- 職員数が少ない中で人間関係がこじれると毎日がつらい
- 保育の質が下がりやすく、保育士の責任や負担が重くなりがち
集団保育のスキルが身につきにくい
小規模保育園では、大集団を動かすスキル力が身につきにくいかと思います。
なぜなら、少人数の子どもと1対1で接することが多く、また、主な保育は、乳児の身の周りの世話や、自由遊びの見守りだからです。
つまり、大人数の子どもたちを動かす保育は経験できません。
こういった、集団保育のスキルは、乳児保育の経験のみではどうしても身につきにくいです。
たとえば、「子どもたちの注目の集め方」とか、「集団を安全に動かすときのポイント」なんかは、日常的に集団保育をすることで自然に身につくものなんですよね。
なので、今は苦手でも、大規模園に転職して経験を積めばそれはちゃんとできるようになるので、それほど心配はいらないですよ。
ただ、ゆったりした自由遊びの乳児保育の経験が長くなると、「集団保育を行う大規模園へ行ってみよう」という勇気は、なかなか出てこないかもしれないですね。
園庭や広いホールがなく、公園に行くことが多い
多くの小規模保育園には、園庭や広いホールがないので、降園に行くことが多いです。
子どもたちに気分転換をさせ、体を動かして思い切り遊ばせたい時には、近所の公園に出かけるしかありませんよね。
なので、保育士は天気の悪い日以外は、ほぼ毎日園外保育をすることになると思います。
しかし、園外に出かける時には、事故や不審者などのリスクがいつも隣りあわせですよね。
さらに、車の往来や不審者などに常に気をつけなくてはならず、保育士は気が休まりません。
もし園庭があれば、公園まで行かなくても気軽に外に出られますし、リスクなく戸外遊びができますよね。
なので、「園庭があればもっと簡単に戸外遊びができるのに…」なんて感じる人がいるかもしれませんね。
一人あたりの仕事が多く休みを取りにくい
小規模保育園は、一人当たりの業務分担が多く、休みを取りにくくなる場合があります。
もともと小規模なので、職員の全体数は少ないですし、保育士が不足してるとなおさら少なくなってしまい、そうなると、一人当たりの仕事がよけいに増えてしまうんです。
たとえば、当番がすぐに回ってきたり、保育以外の事務や雑用が多くなったりしがちなんですよね。
さらに、一人でも休むとそのしわ寄せが他の職員に行くことになり、「気兼ねしてなかなか休みがとりにくい」なんてこともあるんです。
職員数が少ない中で人間関係がこじれると毎日がつらい
小規模保育園は職員数も少ないでが、そんな中で人間関係がこじれると、逃げ場がないので毎日が辛くなってしまいます。
もし、大規模園であれば、クラス替えなどで組む保育士が変わるチャンスがあります。
それがきっかけで人間関係がぐっと良くなることがあるんですよね。
ですが、小規模保育園では、人間関係がこじれた場合でも常に顔をつき合わせることになり、気まずい状況が続いてしまいます。
そんな毎日って、けっこう精神的につらいですよね。
保育士の負担が重くなり、保育の質が下がりやすい
小規模保育園では、有資格者である保育士の責任や負担が重くなりがちです。
B型やC型では保育士(有資格者)の割合が全体の半分か、それよりも少なく、その数少ない保育士が責任を取るしかないんですね。
また、無資格の職員には任せられない仕事は、有資格者である保育士に回ってくるので、その分の負担が増えてしまうんですよね。
そして、保育士有資格者と資格のない職員が同数くらいいると、保育への意識が高い人と低い人が混在して、「保育の質」が極端に下がってしまうことがあるんです。
そのため、保育上の意思統一や連携が取りにくく、いい保育ができなくなってしまうんです。
ひどくなると、園全体にやる気ない雰囲気がただよい、日常的に不適切な保育が行われてしまうこともあります。
そんな環境で働くのは嫌ですよね。
園見学で自分に合った小規模保育園を選ぶ
このように見てくると、「小規模保育園は魅力的な面も多いけど、慎重に選んだ方がよさそうだな」とも思いますよね。
確かにその通りなんですが、では、どうやってあなたに合う小規模保育園を選べばよいのでしょうか。
それはやはり、「園見学をする」ことに尽きると思います。
施設の中や周りの環境を見ておくことも大切ですし、何よりどんな職員がどんな雰囲気で働いているのかを肌で感じることが重要です。
「保育のやり方や子どもへの接し方」「職員の表情が明るく、イキイキと働いているか」などに注目して見学しましょう。
また、質問ができるようなら質問をしてみて、「こころよく答えてくれるか」「答えの内容に納得できるか」といったこともチェックしてみるといいですね。
そうすることで、情報が増えるので、「自分に合う園かどうか」「働いているイメージが持てるか」といったことを考えられると思いますよ。
まとめ

以上、「小規模認可保育園の基準や特徴」「小規模保育園に転職するメリット、デメリット」について、解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
「子どもたちにゆったりと関われる保育がしたい」という思いから、小規模保育園で働きたい保育士の方は多いです。
また、「行事が少ない」「アットホームに働ける」「体力的なゆとりが持てる」などのことからも、人気の職場なんですよね。
競争率も高いので、小規模保育園の転職に挑戦したい方は、保育士転職サイトを使ってみるのも一つの手ですね。
サイトによっては「小規模保育園特集」として小規模保育園の求人をまとめて紹介しているので、自分でも求人検索がしやすくなっていますよ。
記事に書いたように、小規模保育園にはメリット、デメリットがあるので、必ず園見学をして、設備、保育、職員関係などを自分の目でチェックしてくださいね。
あなたの希望の条件と照らし合わせて、あなたに合う小規模保育園を選びましょうね。