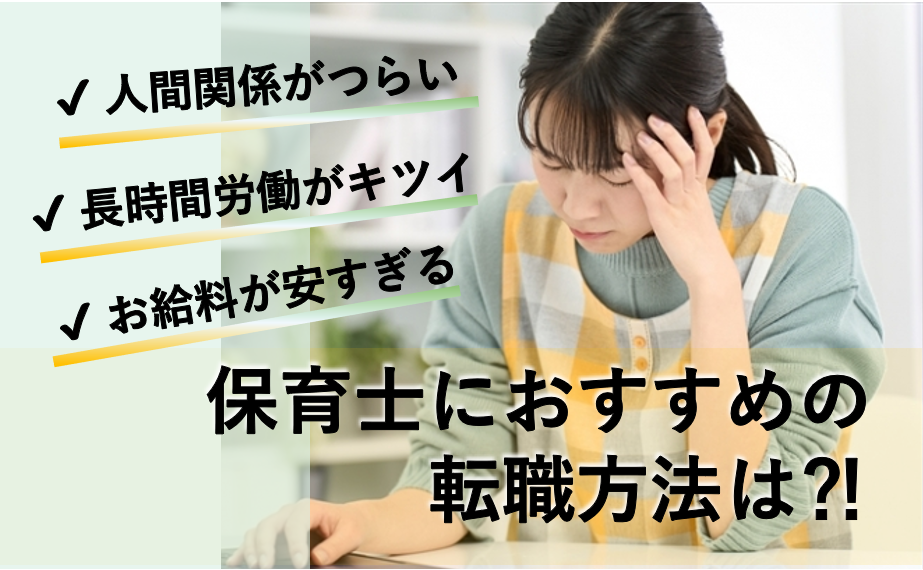こんにちは! 現役保育士はなえみです(転職でホワイト園に巡り会えました!→ プロフィールはこちら)。
毎日気を遣って保育してるのに、また、保護者対応しているのに、クレームを受けてしまったことはありませんか?
保護者から突然不満や要求をぶつけられると、
- 「エーッ、そんな要求まで聞かなきゃいけないの?」
- 「うわっ、また言われちゃったよ~!」
- 「この親、本当に怖い…」
なんて、ドキッとさせられるし、気持ちがズーンと落ち込んじゃいますよね。
今回は、今まさに保護者からのクレームで悩んでいる人、また、クレームが来たらどうしようとドキドキしている保育士の方に向けて、「保護者からクレームが来た時の上手な聞き方と対応方法」と、さらに、「クレームを生まない秘訣」について解説します。
実は私も、実際に保護者からクレームを受けたことがあって、その経験からクレーム対応の難しさを学んだんですよね。
この記事を読めば、保護者からのクレーム対応のコツがわかるので、良好な関係を作ることでクレームを生まずに済みますよ。ぜひ参考にしてくださいね。
目次
実際にあるクレーム(苦情や要求)とは?
クレームは、保護者の小さな不満が積み重なると、それがいつしか爆発して起こることが多いです。
あるいは、これまでは良好な関係だったのに、ある出来事がきっかけで保護者が大きな不信感を抱いてしまうとクレームに発展することもあります。
それでは、実際によくあるクレームを、いくつか見ていきましょう。
クレームと一口にいっても、ちょっとした小さなことから、かなり大ごとになってしまうものまでいろいろありますよね。
たとえば、
- 友だちの汚れ物がうちの子の汚れ物袋に入っている!
- こちらが連絡したことが担任全員に伝わっていない!
- 夕方迎えに行くと朝はなかった傷があるのだが、保育士は何も言ってくれない!
- うちの子に噛みついた子どもの親から謝罪がない。ちゃんと伝えてくれているのか⁈
- 蚊に刺されないようにしてほしい!
- ○○ちゃん(嫌いな子)とうちの子を同じグループにしないで欲しい!
- うちの子をお遊戯会の主役にしてほしい!
- 保育室やトイレや廊下など、どの程度の掃除をしているのか? 衛生面が気になる!
- アレルギーじゃないけど、うちの方針なので牛乳を飲ませないで欲しい!
- 病み上がりなのでお散歩に連れて行かないで欲しい!
- 発熱のたびに職場に電話を入れられても困る!
- 医者でもらった風邪薬をお昼に飲ませて欲しい!
いやー、ホントにいろいろな要求がありますね (-_-;)。
中には、言われても仕方がないものもあって、それは、真摯に反省して改めないといけないです。
ですが、「まあ、気持ちはわかるけどね…、でも保育園じゃできないよね」というものがほとんどで、さらに、「どう考えても自己中だろ!」と言いたくなるようなものもあります。
あなたが言われたことがあるクレームは、どんな感じでしょうか? もっと強烈な内容でしょうか?
いずれにしても、このようなクレームが来たとしたら、どんな保育士でも「えっ⁈ どうしよう?」と焦りますし、穏やかではいられませんよね。
時間がたつにつれて、「なんでそんなこと言われなきゃならないの⁈」とムカムカしてきたり、「あー、また園長と話し合わなきゃ…」なんて気が重くなったりしてしまいます。
園にクレームを入れる保護者の心理とは?
それでは、保育園にクレームを入れる保護者の心理、背景とはどんなものなのでしょうか。
クレームに対応をするにも、相手、つまり保護者を知っておかなければならないですからね。
それは、次の5つがあると思います。
- 自分の子をしっかり見ていて欲しいという気持ちがある
- 共働きで時間に余裕がなく疲れている
- 子育てへの不安がある
- 権利意識が強い
- 保育園への期待度が高い
自分の子をしっかり見ていて欲しいという気持ちがある
まず、「自分の子どもをしっかり見ていて欲しいという気持ちがある」ということですね。
これは、親なら誰でもそうでしょう。
誰でも自分の子は可愛い、だからこそ、仕事で面倒を見られない自分に代わってわが子をしっかり見ててほしい、気にかけてほしい、と思っているんですね。
つまり、「注目してほしい」という欲求なんです。
たとえば、子どもに、「へー、○○作ったんだ~」なんて注目してあげると、すごく喜ぶし張り切るじゃないですか。
大人だって、仕事で成果を上げた時に、同僚や上司に注目してもらえるとうれしいですよね。
それと同じなんです。
なので、保護者も、「自分やわが子に注目してくれてない」と感じると、不満につながってしまうんですね。
共働きで時間に余裕がなく疲れている
次に、「共働きで時間に余裕がなく疲れている」ということです。
特に、母親は、仕事プラス、家事も子育ても自分が中心になってやることが多く、父親に比べてかなり負担を背負っています。
近くに自分か夫の実家があって、祖父母の助けが得られればまだいいのですが、そんな保護者ばかりではないですよね。
さらに、早番から延長番まで子どもを預けている長時間勤務の保護者や、土曜日も仕事がある保護者もいます。
このような背景があって、保護者は常に疲れていたり余裕がなかったりするため、保育士からちょっと何か言われたことが気に障って反感につながってしまうんですね。
子育てへの不安がある
それから、「子育てへの不安がある」という心理もあります。
年上の兄弟を育てたことがある保護者であれば、それほどでもないかもしれませんが、初めての子どもの場合、保護者は子育てへの不安があるものです。
たとえば、本を読んだりネットで情報を探しながら、またはママ友や自分の親に聞いたりしながら、子育てをがんばっているんですが、うまくいかないこともたくさんあります。
「食べてくれない」「寝てくれない」「夜泣きする」「ヤダヤダばかリ言う」「すぐに風邪をひく」など、保護者の悩みや不安は尽きません。
そんなとき、保育士から何気なく言われた言葉が、自分へのダメ出しのように聞こえてしまうことがあるんですね。
自分のやっていることが否定されたかのように聞こえてしまうことがあるんです。
それで不満を持つようになってしまうんですね。
権利意識が強い
続いて、「権利意識が強い」ですね。
たとえば、「これだけの保育料を払っているんだから、それ相応の保育をしてもらえて当然」といったような感じです。
つまり、「わが子や自分たちの利益を守るためなら主張するのは当然の権利」といった思考ですね。
こういった、権利を主張するような考えになってしまうのは、その保護者の視野が狭くなっているのかな、と思います。
だって、子どもが可愛いのはどの保護者も同じですよね。
そんな保護者がみんなして、「うちの子を劇の主役に!」なんて言ったらどうなるか、といったことも想像できないんだと思うと、ちょっと悲しいですよね。
「その要求は、保育園という集団の中で対応できることなのか」「家庭では簡単にできても、保育園ではかなり負担になることもある」ということに思いが至らないでしょうね。
それで、理不尽でわがままとも取れる要求が出てくるんだと思います。
保育園への期待度が高い
最後に「保育園への期待度が高い」ということですね。
かわいいわが子を託すからこそ、「保育園は理想的な場所であってほしい」と、保護者は期待しています。
それは、「安全に子どもを遊ばせてほしい」とか、「誠実に丁寧に対応してほしい」とか、そういったささやかな願いがほとんどだと思います。
それなのに、「園でケガをしたのに何の報告もない」「子どもの衣類が行方不明になったのに探してくれない」といったことがあると、期待が裏切られたと感じて、クレームになってしまいます。
つまり、「保育園にはいつも誠実でいてほしいし、頼れる存在であってほしい」と思うからこそ、クレームを言ってくるということもあるんですよね。
ただ、中には、「トイレっとトレーニングをしてほしい」「お箸の使い方を教えて欲しい」といった家庭でするべきことも保育園にお願いされてしまう場合があります。
これも、一種の期待? なのかもしれませんが、「それは家でやってよ」と思いたくなりますよね。
ですが、それぐらい、保育園の存在は保護者にとって大きいのではないでしょうか。
クレームは怒りではなく悲しみ
このような保護者の心理状態や環境的な背景がわかると、「クレームは怒りではなく悲しみ」だということがわかります。
つまり、
- 「先生に気にかけてもらえなくて悲しい」
- 「時間に余裕がなく疲れているのに、先生に注意されてしまって悲しい」
- 「不安を抱えながら子育てしているのに、先生からダメ出しされて悲しい」
- 「保育園への期待が裏切られて悲しい」
ということなんです。
クレームを言っている真っ最中は、声を荒げて鬼のように怖いかもしれませんが、心の中は悲しんでいるんです。
だから、「クレーム対応とは、保護者の悲しみを聞いてあげること」なんだと思います。
そう思うと、少しだけ気持ちが楽になりませんか?
それに、保護者の方も、クレームを言うか言わないか、かなり葛藤しています。
保護者にしてみれば、「子どもを人質に取られている」と思っているので、そう簡単に苦情は言えないものなんです。
だからこそ、クレームを入れるというのは相当な勇気と覚悟を持ってしているはずなんです。
あるいは、その場の勢いでワーッと言ってしまったようなクレームなら、後になって、「ちょっと言い過ぎたかな…」なんて反省していることもあると思います。
つまり、クレームを入れてくる保護者のことを、「自分の悲しみを知ってほしくて訴えてきたんだな」と受け止められれば、それほど恐怖に感じなくても済むと思いますよ。
【実体験】クレーム対応の4つのポイント
それでは、いよいよクレーム対応の4つのポイントを具体的に解説しますね。
私も、実体験としてクレームを受けたことがあるので、その経験を交えてお伝えしますね。
手順としては以下の通りです。
- 保護者の話を十分に聞き、言い分を受け止める
- 誠意をもって謝罪する
- 即答できることなら、丁寧に答える
- 即答できないことは、「園長と相談します」と答える
では、一つずつ解説しますね。
1 保護者の話を十分に聞き、言い分を受け止める
まずは、保護者の話を十分に聞き、言い分を受け止めます。
これは、私が実際にある保護者から訴えられたことなんですが、
と言われたんですね。
この時、私がどう受けたかというと、
という感じでしたね。
他にもRちゃんママは、Kくんママに関していろいろと不満を言っていたんですが、私は、「そんなことがあったんですね」「それはタイヘンでしたね」としっかり言い分を受け止めるようにしました。
ちなみに、話を聞いているときは、保護者の言葉を「意味の近い別の言葉」に置き換えて繰り返すと、「受け止めてもらえた!」と思ってもらいやすいですよ。
上の場合だと、「謝ってきてくれない」→「連絡くれない」といった感じで言いましたね。
そして、「こういったことが嫌だったんですね」「悲しかったんですね」などと保護者の気持ちを言語化します。
上の場合だと、「何にも言ってもらえないとそれは悲しいですよね」といった言葉ですね。
こんなふうに保護者の言い分を認めてあげるようにすると、「わかってもらえた!」という気持ちになります。
保護者の話をさえぎったり、「えー、でも、私はちゃんと伝えましたし…」「そう言われても…」といった、否定的な相づちや答え方はNGですよ。
2 誠意をもって謝罪する
次に、誠意をもって謝罪します。
上の例の続きで言うと、
といった感じに言えるといいですかね。
本当なら、このようなクレームが来る前に、こちらからRちゃんママに、「あれから、Kくんママから何か連絡ありましたか?」って様子を聞くべきだったな、と反省もしました。
つまり振り返れば、今回の私の一連の行動は、Rちゃんママからクレームが来ても仕方ないような、まずい状態だったんですね。
なので、最後にRちゃんママには、
といった謝罪が必要ですよね。
そして、
なども付け加えるといいかもしれませんね。
このクレームを言ってくれなかったら、Rちゃんママはずーっと一人でもんもんと悩んで、Kくんママや園に対して不満をさらにため込んでいたでしょう。
その気持ちを園に打ち明けてくれたことは、ありがたいことだと思った方がいいですね。
3 即答できることなら丁寧に答える
続いて、即答できることなら丁寧に答えましょう。
上のクレームの場合だと、その場で自分なりの解決策が浮かぶかと思いますが、
たとえば、
といった答えが言えるかと思います。
つまり、クレームの内容によっては、YESかNOかの自己判断がその場でできるはずです。
できることであれば気持ちよく、「わかりました!」と答えるようにすれば、保護者の満足度や、園への信頼度は高まります。
ただ、無理なことやできないことは安請け合いしない方がいいです。
後で、「やっぱり無理です」と伝えると保護者の不信感に、再び火をつけることになってしまいますからね。
4 即答できないことは、「上司と相談します」と答える
もし、即答できないことであれば、「園長と相談します」と答えます。
たとえば、以下のようなクレームが来たとします。
みたいな要求があったとします。
これについては、クラスだけの問題ではなく、園のシステムにも関わってくることなので、即答せずに、
といった感じで、いったん持ち帰ることを伝えましょう。
内容によっては、園長ではなく、「クラス担任で話し合ってみますね」と答える場合もあると思います。
とにかく、一人で背負わないことです。
困ったら、一緒に組んでいる保育士や主任や園長などに伝えて、関係者で集まって話し合ったり、職員会議で議題に上げたりして、対処法を模索します。
ただし、「検討します」と言った以上は、必ず何らかの答えを出して保護者に伝えましょう。
出した要求に何も回答がないと、保護者はさらに不信感を募らせます。
時間がかかりそうなときは、いつ回答できるかも言っておくとよいですね。
クレームは、受け入れたくてもできないものもあり、それはそれで仕方のないことです。
でも、「園でちゃんと話し合いましたよ」という誠実な姿勢を見せることが大事なんですよね。
100%はムリでも、「部分的ならできる」とか、「こういう工夫ならできる」ということがあれば、そういった形で答えていくのもアリですね。
保護者のタイプや要求の内容によっては、担任よりも園長から回答してもらう方がいいこともあります。
もし、自分で要求を断らなければならないときは、言い方に注意が必要です。
「申し訳ありませんが…」「申し上げにくいのですが…」などと頭につけて話しましょう。
また、最後に「ご希望に添えなくて申し訳ありませんでした」「今後も何かありましたら、遠慮なくおっしゃってくださいね」などと、付け加えましょう。
要望がすべて叶わなくても、検討した結果を誠実に丁寧に答えてもらえれば、保護者は、「言ってみてよかった」「気持ちがすっきりした」と思うはずです。
クレームを生まないためにできること
クレームを受けるって、ショックで気持ちが暗くなりますし、できるだけないほうがいいですよね。
では、クレームを生まないためにできることとは何でしょうか。
それは、普段から保護者とのコミュのケーションを心がけるということです。
そうすれば、保護者にも親しみを持ってもらえ、いずれ信頼関係が生まれてくるため、何かあった時も対処しやすいです。
具体的には、
- 子どもの姿を伝える
- トラブル後にはプラスαの気遣いをする
- 何気ない会話をする
といったことでコミュニケーションを取るといいですね。
1 子どもの姿を伝える
毎日でなくてもいいですが、保護者には一言簡単にでも子どもの姿を伝えられるといいですね。
たとえば、
- 「今日は、お友だちと一緒に三輪車に乗って元気よく走り回っていましたよ」
- 「今日は、お当番だったんですけど、張り切ってお茶碗を運んでくれましたよ」
といった感じの、何気ないことで全然OKです。
あるいは、
- 「ずいぶん歩くのが上手になりましたよね」
- 「砂場でお片付けの時間になったとき、赤ちゃん組のお友だちの分まで片付けてくれてたんですよ」
など、子どものいいところをほめるのも効果的です。
これをすることで、「あなたのお子さんにちゃんと注目してますよ」ということが保護者に伝わり、安心感につながります。
早番や延長番などで保護者に直接会えないなら、連絡帳に「ほめポイント」を書くのもいいですね。
保護者は、担任からの連絡帳のコメントを毎日楽しみにしているものなんですよ。
そこで、わが子をほめてもらえたらすごくうれしいと思います。
2 トラブル後にはプラスαの気遣いをする
もし、トラブルやハプニングがあったら、その後にはプラスαの気遣いをしましょう。
ここでも、「保護者や子どものことをちゃんと気にかけてますよ」ということを伝えるんです。
たとえば、子どもがケガをした時には、その後のフォローって特に大切ですよね。
ケガの程度が軽ければ、遅番や延長番の先生にケガのことを保護者に伝えてもらうよう、しっかりと申し送りしましょう。
そして、夜には保護者に電話入れましょう。
「今日は、ケガをさせてしまい申し訳ありませんでした。○○ちゃんの様子はいかがですか?」と電話を入れるとグッと好印象になります。
もし、ちょっと重めのケガの場合は、担任が保護者のお迎えを待ち、直接会ってケガの件を伝え謝罪しましょう。
そして、次の日の朝にも、「今朝はどんな調子ですか?」と昨夜から朝にかけての様子を尋ねます。
もし、保護者が早番で来るため担任と会えない場合は、早番の保育士に一言、「○○ちゃんが朝来たら、ケガのことを確認してください」ということも伝えておきましょう。
担任はもとより、当番の先生までケガのことを知っていて気にかけてくれたら、保護者はうれしいですしさらに安心しますよね。
3 何気ない会話をする
そして、普段から何気ない会話をするようにしましょう。
内容はなんでもいいんです。
たとえば、
- 「今日も暑かったですね。お仕事お疲れさまでした」
- 「おはようございます! わー、今日の○○ちゃんの洋服、涼しそうー」
- 「最近暗くなるの、早くないですか? もうこれからどんどん寒くなりますよね」
とか、ホントに何でもいいんですよ。
担任にとっては、保護者は大勢の中の一人ですが、保護者にとってはたった一人の担任です。
そんなことでも話しかけられると、保護者は、「あ、先生、私に話しかけてくれてる」とうれしくなるものなんですよ。
クレームは期待の裏返し、保護者は怖くない!
保護者からのクレームは、保育士にとって嫌なものです。
ですが、見方を変えれば、クレームを言ってくれるのは、「園にもっとよくなってほしい」という期待があるからです。
もちろん、すべての期待に応えることはできませんが、クレームに対してどう検討してどう答えるか、そのプロセスが大事なんです。
保護者にとっても結論は大事ですが、それより、「真剣に受け止めてもらえたか」「解決に向けて努力してくれたか」といいうこともすごく大事なんです。
つまり、保護者の気持ちをしっかりと受け止めた上で、誠心誠意努力したことを、真摯に説明することで、園の姿勢は伝わるのではないか、と思います。
そうすることで、「雨降って地固まる」じゃないですけど、今までよりも良い関係が築けることもあるんです。
だから、保護者って無理難題を言ってあなたを攻めてくる怖い存在ではないんです。
もちろん、完璧でもありません。
わが子を必死に守りたい、不安でいっぱいの迷える親なんですよ。
そう思って、保育士はそんな保護者を丸ごと受け止めてあげるくらい、大きな気持ちでいましょうよ。
そして、クレームを言ってくる保護者を避けたりしないで、あえてこちらからあいさつするなど、積極的に声かけしていきましょう。
まとめ
保育士にとって保護者は、上手に信頼関係を築かないといけない相手であり、とても気を遣いますよね。
ですが、本当はどの保護者も子育てに悩んだり迷ったり不安になったりして、さらに仕事もタイヘンで、一杯いっぱいなんですよ。
そんな気持ちが高じると、ちょっとしたことに反応して、それが園へのクレームに発展してしまうんですよね。
クレームは、「うちの子をしっかり見てほしい」「園にもっとよくなってほしい」という、希望と期待の気持ちの裏返しなんです。
なので、保護者のことを、「怖い」「自己中」「面倒な人」などと決めつけないで、保育のプロとして大きな心で受け止めていきましょう。
「雨降って地固まる」って言いますが、同僚や上司と相談し、連携し合ってクレームに対応し乗り越えられれば、保護者との関係をよりよいものに深められるはずですよ。