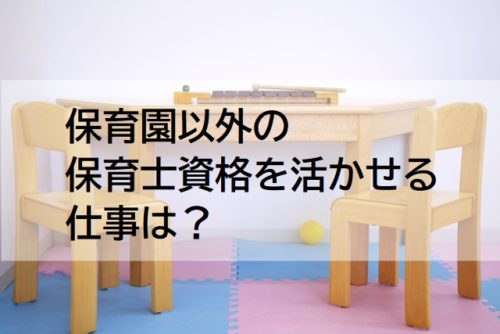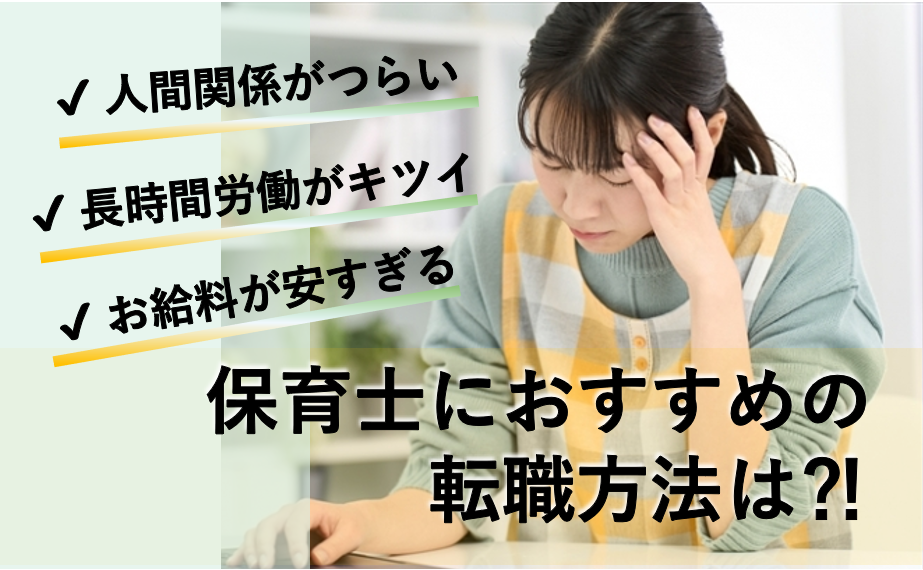こんにちは! 現役保育士はなえみです(転職でホワイト園に巡り会えました!→ プロフィールはこちら)。
今は保育園で働いているけど、もう限界を感じて、転職を考えている保育士の方は多いです。
たとえば、
- 「もう保育園で働くのは嫌だな…」
- 「保育園は嫌だけど、できれば保育士資格を活かして働きたい…」
なんて思っていませんか?
この記事では、保育園以外の施設で保育士資格を活かして働きたい方に向けて、「保育士資格を活かして働ける、保育園以外の仕事」について解説し、その仕事内容とやりがいもお伝えします。
保育園以外で保育士資格を活かして働ける所ってけっこうあることがわかりますよ。
転職先として選択肢に入れるのもアリですね。
目次
保育園以外で保育士資格を活かして働ける仕事とは?
では、保育園以外で保育士資格を活かして働ける仕事について、挙げてみましょう。
それは以下のようになります
- 託児所
- 病児保育
- 病棟保育
- ベビーホテル
- ベビーシッター
- 幼児教室
- プリスクール
- 保育ママ
- 学童保育
- 放課後等デイサービス
こう見てみると、かなりの種類がありますよね。
それぞれが施設ごとの目的や特徴を持っていますので、保育園の仕事とはまた違った勤務内容にはなりますが、保育士資格を活かせるし、保育士資格があると有利な場合が多いんです。
それでは一つずつ詳しく見ていきましょう。
託児所
託児所は、認可外保育施設に分類されます。
保護者が仕事のときだけではなく、さまざまな用事で子どもを預けたいとき、一時的に預けられるのが託児所です。
一時的と言っても幅があり、「月極保育」や「一時保育」など、預かる形態は、保護者のニーズによってさまざまです。
たとえば、「イベント参加のため」「美容院や歯医者を利用する間」「デパートで買い物をする間」「臨時の仕事が入ったので1か月だけ預けたい」など、保護者の仕事や用事をスムーズに済ませるため、その間子どもを預かります。
たとえば、イベントの託児所であれば、そのイベント時間のみ預かりますし、レジャー施設の託児所であれば朝から夜までオープンする場合がありますよね。
つまり、託児所の目的によって保育時間は異なり、保育士の勤務時間やシフトも変わります。
また、保育する子どもはその日ごとに違い、年齢も乳幼児とは限らず小学生を預かることもあります。
託児所は、基本的に少人数の場合が多く、保育園のように行事もないので仕事量はそう多くはありません。
残業や持ち帰り仕事などもないでしょう。
託児所の職員は保育士資格がなくてもOKですが、求人を見ていると保育士資格を必要とするものも見かけるので、施設によりけりです。
そして、託児所の特徴としては、日々預かる子どもの顔触れが変わり、保育士との関係性もその場限りのことが多いです。
なので、保育園のように継続的に子どもに関わり成長を見届けることはないですが、預かっている時間の中で、子どもが安心して楽しく過ごせるように精一杯保育しようという心構えが大切ですね。
病児保育
普段、保育園に通っている子どもが急に発熱したり、ケガをしたりしたときに、働く親に代わって子どもを見るのが病児保育です。
病児保育には、子どもの自宅に保育士が訪問して保育する「訪問型」と、施設に親子で来てもらって子どもを預かる「施設型」があります。
病児保育をする保育士のことを、「病児保育士」と呼ぶことがありますが、それは、「保育士資格を持つ病気の子どもを専門に保育する人」という意味で、国家資格ではありません。
ちなみに、一般社団法人全国病児保育協議会では、専門の研修後に一定の水準に達すると、「病児保育専門士」という民間資格を認定しています。
そういった認定資格を持っていると、自信を持って病児保育のお仕事ができますよね。
病児保育士の働き方ですが、訪問型の場合は、保育士が病気やけがの子どもの自宅に出向きます。
子どもの病状を親から聞き取り、食べ物や飲み物、飲ませる薬などを預かります。
預かっている間は、病状に合わせて看病したり、食事や排せつ、着替えなどの世話をしたり、一緒に遊んだりして過ごします。
通院を頼まれれば、お医者さんに連れていくこともあります。
時には、体調が急変することもあるので、緊急の時にはどう対応するか、親との連絡方法などもしっかり確認し合っておく必要がありますね。
そして、親が仕事から帰ってきたら、今日1日保育で行ったことや病状、子どもの様子などを伝えます。
子どもは病気なので、健康なときとは違って、体がつらかったり精神的にも不安定になったりすることがあります。
ですが、そんな気持ちを受け止めながら、安心して過ごしてもらえるように、温かい気持ちで丁寧な保育をする必要がありますね。
もちろん、子どもの発熱やよくかかる病気についての知識や、症状別の対処法なども知っておく必要があります。
一方、施設で病気の子どもを預かる「施設型」の場合、病院の中や近くに病児保育の施設を構えていることが多いです。
親に子どもを施設まで連れてきてもらい、その日の着替えや食事、飲み物、薬なども持参してもらいます。
病状に合わせて、1日施設で寝たり遊んだりして過ごし、病児保育士が病気や生活の世話をします。
必要に応じて、併設の病院で受診したり、受診によってもらった薬を飲ませたりすることもあります。
お迎えに来た親に、今日1日の子どもの様子を伝えるのは保育園と同様ですが、より細かな様子を丁寧に報告する必要がありますね。
このように、病児保育では、まずは子どもの病状を把握し保育中もその変化を見逃さず、適切な対処をすることが重要です。
また、病気で不安になっている子どもが安心できるよう、ゆったりと構えて受け止めるのはもちろん、病気の子どもを置いて仕事に行かなくてはならない親の辛い気持ちも受け止めてサポートする心構えが必要ですね。
病棟保育
病棟保育とは、病気やケガで入院している子どもの保育に当たることを言います。
そこで働く保育士は、「病棟保育士」とか、「医療保育士」などと呼ばれます。
病棟保育士の仕事は、入院している子どもの保育や生活面(食事、排せつ、着替えなど)の介助などが主になります。
また、環境の衛生面には注意を払い、プレイルームの清掃や玩具の消毒などを行います。
一人ひとりの病状に配慮しながら、安心・安全に保育ができるようにしています。
保育の形態は、子どもの病状にもよりますが、小集団で遊びや活動ができる状態の子どもであれば、プレイルームなどで病棟保育士が楽しめる遊びを提供します。
年齢はまちまちになることもありますが、子ども同士で遊びを共有することで、お互いが親しみを持ち仲良くなれるよう、病棟保育士が橋渡しをします。
もし、子どもの病状によって集団参加が難しい場合は、個別に遊びを提供することもあります。
また、子どもが小学生以上であるときは、学習支援もしますし、話し相手になることもあります。
さらに、季節に応じた行事を看護師と協力して企画することもあります。
とかく、入院生活は単調になりやすいので、子どもやその家族がいつもとは違う雰囲気の中でイベントを楽しんでもらえるようにします。
いずれにしても、病中の子どもが対象なので保育の場所が入院施設内なのでできることが限られてしまうこと、そして中には精神的に不安定になっている子どももいるなど、配慮すべき点が多いのが病棟保育です。
そんな中で細かな気配りをしながら、子どもの生活支援や遊びの提供、学習支援など、ニーズに合わせた幅広いサポートが求められます。
そのためにも、医師や看護師の毎日の申し送りに参加したり、定例カンファレンスに参加したりなど、子どもやその家族についての情報交換は欠かせません。
その情報をふまえた上で、保育上の注意点を理解しておく必要があります。
また、入院している子どもの保護者支援も重要な仕事です。
保護者は、子どもの入院で、気持ちも生活自体も不安定になり、ストレスを抱えていることが多いです。
なので、保護者には保育中の子どもの様子を細かく伝えたり、子育てや家族の相談に乗ったりなど、保護者の悩みに寄り添う役割もあります。
そんなふうに、保護者と病棟保育士が親しく話している様子を見ることで、子どもも病棟保育士への信頼感を持ち、良い関係が築ける、という副産物もあるんですよ。
病棟保育士になるには保育士資格があればOKですが、入院中の子どもの支援を行う立場として、簡単にでも医療や看護に関する知識を頭に入れておくとよいですね。
ちなみに、日本医療保育学会では、「医療保育専門士」の認定資格を設けています。
これは、保育だけでなく医療や看護からの視点も取り入れた病棟保育について、専門性を磨くことによって得られる資格なんですね。
病棟保育士は、その専門性を活かし、ストレスの多い入院生活であっても、病気の苦痛や不安を少しでも忘れて過ごせる時間を提供します。
また、子どもが楽しい時間を過ごし笑顔が増えることで、家族も笑顔になれるような支援を志しています。
ベビーホテル
ベビーホテルとは、認可外保育施設の一種であり、東京都福祉保健局では、
- 夜19:00以降の保育を行う
- 宿泊を伴う保育を行う
- 時間単位での児童の預かりを行っている
という、「3つの条件が、どれか一つでも当てはまる施設をベビーホテルと呼ぶ」と定義しています。
たとえば、
- 「朝7:00~夜21:00まで開園している」
- 「24時間開園している」
- 「夜19:00~朝5:00までの夜間のみ開園している」
- 「一時保育など、利用者の希望によって時間単位の保育をしている」
という園であれば、それぞれベビーホテルというカテゴリーに入ります。
こう見てみると、ベビーホテルに当てはまる認可外保育施設の幅はかなり広いですよね。
「託児所」の機能に、「夜間保育」や「24時間保育」が加わったイメージでしょうか。
そんなベビーホテルですが、ここでは、24時間開園していたり、夜間のみ開園していたりするようなベビーホテルについて解説したいと思います。
24時間開園している施設でも、「ベビーホテル」と名乗っていることは少なく、「○○保育園」「△△保育室」「□□キッズルーム」など、さまざまな名称で運営しています。
なので、パッと見には普通の認可外保育園に見えます。
でも、保育時間や保育方針などを見てみると、「24時間対応の親切な託児所」「24時間子育てを応援します」などとうたっている場合があり、そこで初めてベビーホテルの機能があるとわかります。
ベビーホテルで預かる子どもは乳幼児だけとは限らず、小学生の場合もあります。
保護者が預けるときの理由は仕事だけに限らず、どんな用事でもOKです。
なので、毎日通う子どももいれば、一時的に預けられる子どももいますし、異年齢での合同保育になることも多いでしょう。
このようなベビーホテルですが、保育理念や保育方針をしっかり持ち、保護者支援にも熱心に取り組んでいる施設もあります。
たとえば、講師を招いての特別保育プログラム(体操教室、リトミック、英会話など)を実施し、季節の行事や食育などが充実している施設も多いです。
また、共働きやひとり親家庭で子育てを頑張っている保護者のために、柔軟に子どもを受け入れ、きめ細かなサービスを行っている場合があります。
保育士が、このようなベビーホテルで働く場合、ネックになるのはやはり夜勤でしょう。
夜勤があると生活リズムが不規則になり、体調を整えにくくなりますからね。
ですが、夜間に子どもを預けては働く保護者は、そうしなければ生活ができない複雑な事情を抱えていることが多いです。
そんな保護者や子どもにとって、夜間でも子どもを預かってくれるベビーホテルの存在はとても大きいです。
ベビーホテルで働くことは、このような保護者や子どものために貢献できるので、大きなやりがいになるでしょう。
保護者に安心して仕事をしてもらえるよう、また、子どもが夜間に保護者と離れても、安心して過ごせるような居場所づくりをすることが、保育士としての大事な役割といえます。
ベビーシッター
ベビーシッターは、依頼者である保護者のお宅に伺って、子どもを預かり保育する仕事です。
または、依頼者の自宅以外の場所で子どもを保育したり、保護者に代わって子どもを送迎したりすることもあります。
シッターの対象は乳幼児だけでなく、小学生や中学生の場合もあります。
ベビーシッター自体は公的な資格ではなく、民間資格として「認定ベビーシッター」というものがあります。
もし、保育園での保育士経験や、幼稚園での幼稚園教諭の経験があれば、文句なく信頼されますし、保護者からのオファーも断然もらいやすいです。
ベビーシッターとして働く場合は、
- ベビーシッターの派遣会社に登録する
- マッチングサービスを利用する
- フリーとして仕事を請け負う
といった方法があります。
まず、ベビーシッターの派遣会社に入社すれば、そこの社員として雇われるので、シッターの仕事も安定的に紹介してもらえます。
また、事前研修や、仕事を開始した後にも緊急時の対応法や接遇、保育の研修を行っている企業もあり、ベビーシッターとしてのレベルアップを支えてくれる派遣会社もあります。
また、マッチングサービスを利用する場合もあります。
マッチングサービスとは、子どもの保育を求めている保護者とベビーシッターの橋渡しをしてくれるインターネット上のサービスです。
フリーのベビーシッターがマッチングサイトに登録、ベビーシッターを求めている保護者がサイト内を検索して好みのベビーシッターを見つけ指名します。
さらに、フリーのベビーシッターとして仕事を請け負う働き方もあります。
フリーなので、自由に働く時間、場所、シッター内容、料金などを決められます。
ただ、自分で広告などで宣伝したり、口コミを広げてもらうなど、利用者を集めるための努力が必要です。
保育園での保育とベビーシッターの大きな違いの一つは、保育する子どもの人数です。
保育園は集団保育なので、子どもたちをまとめるのに精いっぱい、一人ひとりに寄り添ってあげられない、といったジレンマがあったと思います。
ですが、ベビーシッターは基本1対1で保育します。
預かる子どもに合わせて、自分の得意とする遊びを提供したり、コミュニケーションも密にとれるので、子どもにじっくりと関わることができます。
また、働き方も保育園に比べてベビーシッターの方が自由度が高いです。
自分の働ける時間帯に合わせて、ベビーシッターの仕事を請け負うことができるからです。
また、保育園のように行事や多くの書類作成もありません。
保護者向けに、シッターをした報告書はその都度作りますが、保育園での業務をこなしてきた保育士の方であれば、難なくこなせる程度のものです。
なので、残業や持ち帰り仕事もなく、生活に時間的なゆとりが生まれます。
ただ、「仕事がコンスタントに入ってくるのか」「シッター自体も保護者とのやりとりも、すべて自分一人の責任で対応しなければならない」などの心配はつきまといます。
そこさえ軌道に乗れば、ベビーシッターは自分の得意分野を活かした保育ができ、また保護者の方からもダイレクトに感謝される仕事であり、やりがいは大きいでしょう。
幼児教室
幼児教室とは、就学前の乳幼児を対象に、知的能力や社会性などを最大限に伸ばすために独自のカリキュラムを提供する場です。
幼児教室を運営する企業はたくさんありますが、それぞれの理念に基づいてカリキュラムが設定されています。
そして、その指導方法を体得した講師が、子どもたちにさまざまな活動を体験させその能力を引き出します。
幼児教室の講師は、既存の教室に出向いて勤務する場合と、自宅で開業する場合があります。
どちらのスタイルで働くかは、幼児教室を運営している企業の運営方針によります。
幼児教室には大きく分けて2種類あります。
一つは、子どもの知的好奇心を満たし、多様な経験を積むことで、その能力を開花させ伸ばすことを目的にしている教室です。
たとえば、知的な能力を伸ばすためには、絵カードを高速スピードで次々と見せていき右脳を刺激したり、一人ひとりに玩具や教材を与えて指示に応じて課題に取り組んだり、数字や文字の読み書きや理解を促したりします。
中には、英語に慣れ親しみ、習得することを目的とし、英語を取り入れたさまざまな遊びや活動を展開する幼児教室もあります。
また、社会性やコミュニケーション能力を高めるために、集団でゲームをしたり歌ったり踊ったりなどの活動を行うこともあります。
それらの活動を通して、講師は子ども一人ひとりに注目し、よいところや頑張っているところをほめながら自己肯定感やさらなる好奇心も育みます。
そして、幼児教室は子どもだけでなく、保護者にとっても貴重な学びの場になっているんです。
たとえば、子どもを指導する講師の声かけや振る舞い方、玩具や教材の与え方や使い方を見ることで、自分の子育てを振り返り、参考にすることができます。
また、子育ての悩みをピンポイントで講師に相談することもできるので、不安が解消され安心して子育てができます。
もう一つのタイプとして、小学校受験に特化した幼児教室があります。
たとえば、受験に必要な、「日常生活や身の周りのことに関する知識や対応力」「数の理解」「文字の読み書き」「集団での適切な行動」などを身につけるためのカリキュラムがあります。
さらに、「面接の練習」として、子どもだけでなく保護者も共に望ましい受け答えの仕方を指導します。
すべては、小学校受験に合格するための多様な力を育むことが、最大の目的となっています。
このように、幼児教室にもさまざまなタイプのものがあり、幼児教室の講師になる場合は、その教室の教育理念に共感できるかどうかが大きなポイントになります。
その上で、「この教室で働きたい!」となれば、その教室独自の研修を受けることで、講師になれます。
どの教室でも、独自の指導方法のマニュアルがあり、それに沿って授業を行うことになります。
なので、それさえしっかり身につければ未経験でも大丈夫ですよ。
特に、保育士資格を持っていて、保育園での勤務経験がある方なら、たとえブランクがあっても大きな強みになります。
保育園での保育は、「生活」「遊び」などが中心ですが、幼児教室は、「わが子の能力を伸ばしたい」という保護者が、明確な目的を持って通ってくる場です。
それだけに、指導のテクニックは必須ですし、責任を持って効果を挙げなければなりませんが、それが逆に大きなやりがいにもなるでしょう。
プリスクール
プリスクールは、まだ耳慣れない言葉かもしれませんが、簡単に言うと英語を使って生活する保育園や幼稚園のことです。
そのほとんどが認可外保育施設に属します。
子どもの対象年齢は0歳から就学前の子どもですが、施設によっては、幼稚園のように3歳児~5歳児としているところもあります。
ちなみに、インターナショナルスクールという言葉は聞いたことがありますよね。
インターナショナルスクールも英語環境で子どもを教育し保育しますが、基本的には、外国で育った子どもを対象に、英語を使って教育するところとされています。
一方、プリスクールは日本の家庭の子どもを英語環境で生活させることで、英語に慣れ親しみ、身につけさせることを目的としています。
ただ、中には「インターナショナルプリスクール」と看板を掲げている施設もあり、その対象とする子どもの厳密な境界線は、はっきりしなくなっているのが実情なんですよね。
プリスクールの保育時間は、保育園のように早番から遅番まで長い時間保育してくれる施設もありますし、幼稚園のように短時間保育のみの施設もあります。
保育スタッフは、ネイティブの発音で英語を話す外国人や、日本人でも英語が堪能な、あるいは英語が好きな保育士などです。
毎日、本格的な英語に触れながら生活することによって、子どもはネイティブな英語を覚えられますよね。
また、外国人のスタッフを身近に感じながら生活することで、グローバル感覚を養うことができます。
プリスクールでの会話は英語のみを使うところと、日本語を併用するところもあり、施設によって方針が違います。
ですが、基本的には英語を使って保育しており、「子どもが自然に英語を耳にし、無理なく習得する」というねらいは共通です。
生活の中で英語を使うだけでなく、英語を使った特別プログラムも行いますが、その他にも運動や音楽など、英語に限らずさまざまな活動を提供し、子どもの能力を伸ばします。
そんなプリスクールで求められる人材は、英語が堪能とまではいかなくても、ある程度分かり話せる保育士です。
外国人スタッフと連携したり、外国人の保護者ともやりとりする場合があるので、英語がいくらかでもわかり、話せる方が望ましいですね。
「英語に興味がある」「英語が好き」「簡単な英語のやり取りならOK」という保育士の方であれば、プリスクールで働くのは、キャリアを深めるチャンスと言えますね。
プリスクールの運営方針や教育理念、求める保育士像などは施設によって違うため、よく調べて理解することが大切です。
保育ママ
保育ママ制度は、平成22年の児童福祉法の改定によって、待機児童解消のために国が定めた、「家庭的保育事業」のことです。
保育ママは、別名「家庭的保育事業者」とも言われ、働いている保護者の子ども(0~2歳児)を保育ママの自宅で預かり保育します。
保育ママ一人当たり、3人までの子どもを預かることができ、保育ママが2人で保育する場合は5人までの子どもを預かれます。
保育時間は8:00~17:00などと、自治体によって基本時間が決められていますが、保育ママの都合がOKなら、保護者の希望が希望する延長保育もできます。
保育ママの収入は、保護者が支払う保育料と、自治体が支払う補助金の合計額です。
金額の決め方は自治体によって違い、また預かる人数によっても変わってきます。
そんな、保育ママとして働きたい場合は、いくつかの条件をクリアし自治体に認定してもらう必要があります。
たとえば、「年齢」「決まった間取りや部屋の広さがある」「未就学児童を養育していない」「看護や介護の必要な親族がいない」などです。
また、保育士資格や保育士経験がなくても、育児経験があればよく、指定の研修を受けることで、保育ママとして認定されます。
保育士資格は必ずしも必須ではありませんが、持っていた方が受ける研修が少なくて済みますし、預ける保護者の信頼は得られやすいですよね。
保育ママは、少人数の乳児を自宅でゆったりと保育でき、自分の思うような自由な保育ができるところが魅力です。
また、一人ひとり子どもにじっくりと丁寧に関わり、愛着を持った関係づくりができるのもよいですね。
子どもの様子を細かく伝えることで、保護者とも密に関わることができ、やりがいがあります。
実は、私は自分の子どもを保育ママさんに預けていた経験があるんです。
乳児のうちは保育園に預けるよりも、「家庭的な雰囲気の中でゆったりとみてほしいな」といった希望があったからです。
また、偶然にも私の家のすぐ近く(歩いて30秒くらい)にお住いの保育ママさんだったので、預けやすかったことも大きなポイントでした。
その保育ママさんはとても優しくいい方だったので、安心して預けることができました。
さらに、保育園のように紙おむつに名前を書く必要がないし、布団カバーもかけないで済むし、行事もないので仕事を休まなくてよいのがとてもよかったです。
ただ、保育ママは一人で保育しなければならないため、急に休むことは避けなければなりませんよね。
なので、風邪を引かないようにするなど、自分の健康には十分に気をつける必要があります。
当時の私も、「保育ママさんって健康じゃないとできないよね。本当に大変だよな」などと思っていました。
そして、保育のことを相談できる同僚が身近にいないことで、心細く思うことがあるかと思います。
また、自分一人で運営していかなければならないので、責任が重く感じるかもしれません。
ですが、自分の自宅で好きな保育ができ、子どもや保護者とも親密な関係が作れるのが、保育園とは違った魅力であり、やりがいになるでしょう。
私が預けていた保育ママさんも、いつも笑顔で私や子どもを温かく迎えてくれていました。
連絡帳に毎日の出来事を丁寧に書いて下さって、それは今でも大事に取ってありますし「本当にありがたかったな」と感謝しています。
学童保育
学童保育は、正式には、「放課後児童健全育成事業」というもので、保護者が働いている小学生を、放課後や長期休みの間に預かる施設のことです。
学童保育には、厚生労働省の管轄で公設公営(自治体が施設を造り運営もする)の施設と公設民営(施設は自治体が造るが、運営は民間に委託)の施設、さらに、完全に民間企業や学校法人などが設置、運営している施設があります。
運営主体が公か民かによってサービスの内容や、保育の対象となる子どもも違ってきます。
まず、自治体が関与しているのが、公設公営、あるいは公設民営の放課後児童クラブ(学童クラブ)です。
保護者が働いていることが条件で、対象年齢も小学校3年生まで(6年生まで可とする自治体もあり)となっています。
保育時間は、下校(13:00以降)から18:00までとしている施設が多く、中には19:00まで延長保育をする場合もあります。
夏休みや冬休みなどの長期休みの際には、朝8:30ごろから預かります。
学童クラブで子どもを保育するのは、放課後児童支援員やその他の職員(学童保育指導員)です。
放課後児童支援員は、2015年から新設された資格で、一定の条件を満たしたうえで、各都道府県の、「放課後児童支援員都道府県認定資格研修」を受けることで資格が与えられます。
条件の中には、保育士資格も含まれているので、持っていれば研修を受けて放課後児童支援員になれますね。
学童クラブの仕事内容は、下校してきた子どもたちを迎え入れ、おやつを食べさせたり、宿題をするように促したりします。
また、遊びのコーナーや製作コーナーを設定したり、子どもたちの遊ぶ様子を見守ったりし、ケンカなどのトラブルに対応します。
子どもたちは比較的自由な空間で、やりたい遊びをして過ごし、職員は子どもたちの安全を守ります。
一方、民間の学童保育は、自治体が関与する学童クラブに比べて、預かる子どもの保護者は働いていなくてもOKだったり、子どもの年齢も問わなかったりなど条件がゆるやかです。
また、預かる時間帯も20:00までなど、夜遅くまで預かってくれる傾向があります。
自由遊びだけでなく、勉強のフォローに力を入れていたり、習い事ができたり、自由遊び以外に特別な活動に取り組むことで経験を広げ、一人ひとりの能力を伸ばすことにも力を入れています。
「平日は働いているから、習い事をさせてあげられない」という、保護者の悩みに応えたサービスを行っているんですね。
どちらのタイプの学童保育でも、子どもたちは小学生なので、もう身の周りのことはたいてい何でもできるので、大人の手はかかりません。
それよりも、いろいろな遊びを提供して一緒に楽しみ、子どもの話をじっくり聞いてあげるなど、幅広い遊びやコミュニケーションを楽しめるところが魅力ですね。
一方、子どもの年齢が高くなってくると、対応が難しいときがあります。
小学生ともなると、理屈っぽくなる、素直になれない、嘘をつく、遠慮して黙ってしまうなど、乳幼児に比べて反応が複雑で、本音が理解しにくい場面もあります。
ですが、職員が子どもの姿をしっかりと観察し、気持ちを汲み取った声かけができれば、お互いに心を通い合わせることもあります。
子ども同士のトラブルもたくさん起こりますが、職員がそれぞれの気持ちを理解しようという立場で寄り添えれば、友達関係をよい方向に持って行けるでしょう。
ただ、子どもによっては気持ちが荒れやすく、暴力をふるったり暴言を吐いたりする子がいます。
それも、子どもに対してだけでなく、職員にもそういった態度を取る子がいます。
そんなときは、より丁寧に子どもの気持ちやそうなってしまう原因などを探り、職員同士でしっかりと話し合い対処方法を考える必要があります。
学童保育は需要が多いにもかかわらず施設が足りていないため、定員が70名とか80名など、保育する集団規模として大きすぎる施設が多いです。
そうすると、子どもたちも落ち着かず、よけいにトラブルが多くなりがちです。
そんな状況だと対応する職員も余裕がなく、冷静な状況判断や適切な対応ができなくなるなど、悪循環に陥りやすいです。
そんな環境でも職員は冷静さを失わず、温かい心を持って子どもたちを受け入れ対応する器の大きさが求められます。
放課後等デイサービス
放課後等デイサービスとは、障害のある小学生・中学生・高校生(6歳~18歳)の子どもが放課後や長期休暇の間に通い、さまざまな発達支援を受けられる施設のことです。
放課後等デイサービスで受けられるサービスは、事業所によって特徴があり目指していることもさまざまです。
たとえば、自由にやりたいことをして過ごす時間も設けながら、運動、楽器演奏、製作、パソコン操作、といった習い事のような活動を提供する施設があります。
あるいは、学習をサポートしたり、身辺自立のための生活スキル、豊かなコミュニケーションを取るための社会性スキルなどを身につけることに力を入れているところもあります。
または、地域交流をしたり、博物館や工場見学に出かけたりなど、積極的に外に出向いて社会経験を広げるプログラムを行うこともあります。
これらの多彩な支援の一つを特化させて提供していたり、いくつかのプログラムを組み合わせたりなど、施設ごとに特徴を打ち出しています。
発達につまずきを抱える子どもたちは、放課後や長期休みの間に、自主的にやりたいことを考え、それを実現させる方法や段取りを導き出すことが難しいです。
また、学校での悩みやトラブルが多くなりがちですが、かといって家庭ではフォローしきれないことも多いです。
そんな子どもたちが、放課後や長期休みに間に、好きなことや新しいことにチャレンジし経験を広げることで、楽しめることを増やし、イキイキと余暇を過ごせるように支援するのが放課後デイサービスです。
また、学校や家庭生活の中でできることを増やしより充実させるために必要な、生活スキルや社会性スキルを身につける場としての役割も担っています。
そんな放課後等デイサービスで、直接子どもたちに活動を提供し指導し、支援するのは児童指導員や保育士です。
なので、保育士資格を持っていれば、スムーズに転職できるでしょう。
一方、児童指導員は、「任用資格」であり、国家資格である保育士とは違うカテゴリーです。
児童指導員として採用されるための条件がいくつかあるので、それをクリアした上で応募し、施設に採用されることで、初めて児童指導員と名乗れるんですね。
放課後等デイサービスでは、発達に課題がある子どもへの支援となるため、常に試行錯誤です。
もちろん、他の子どもで成功した支援を応用することもたくさんありますが、一人ひとりの発達の特性は違うので、子どもに合った関わり方を工夫しなければうまくいきません。
そのためには、支援にあたるスタッフの話し合いや連携がとても重要になります。
そのような、細やかな配慮や工夫や反省を重ねながら、子どもと深く密に関われる放課後等デイサービスの仕事はとても興味深いものです。
保育士としてのスキルも一段と上がり、貴重な経験となるはずです。
まとめ

保育園以外でも、保育士資格を活かして働ける仕事って、いろいろとあるんですよね。
もちろん、保育園とは違う働き方になるので、最初は戸惑うかもしれませんが、保育士として子どもに関わることに変わりはありません。
保育園のときとは違った形で子どもや保護者のために貢献でき、やりがいを感じられますよ。
もし、保育士資格を活かしながら保育園以外の仕事をしてみたい方は、保育士転職サイトに相談してみるといいです。
保育園以外の求人も取り扱っているので、その仕事内容についても詳しく教えてくれますよ。
保育園以外で保育士資格を活かせる仕事に転職するのは、キャリアの幅を広げるのにピッタリですし、子どもと接するのに慣れているので無理がないですよね。
今まで保育園で働いてきた経験は必ず生きるはずですし、あなたの強みとしてアピールできます。
ぜひ新しい世界にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。