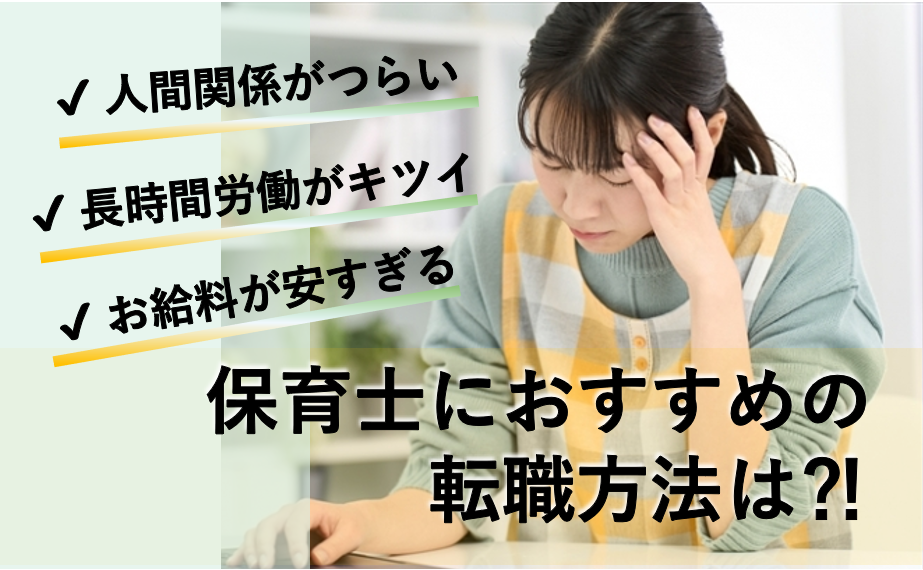こんにちは! 現役保育士はなえみです。
(転職でホワイト園に巡り会えました!→ プロフィールはこちら)
保育園で働いていると、あまりにも忙しい、そして大変っ!
そんなとき、「保育園より幼稚園の方がよかったのかな?」なんて、思ったりしませんか?
他にも、
- 「幼稚園ならもう少し、仕事も楽なんじゃないかな?」
- 「幼稚園と保育園ではどっちの方が給料が高いんだろう?」
- 「幼稚園って、夏休みもあるしいいよね~」
なんて思うと、幼稚園への転職も考えられますよね。
今回は、
- 「幼稚園と保育園の制度や資格」
- 「仕事内容の違い」
- 「お給料の実態」
まで詳しく解説します。
この記事を読めば、幼稚園と保育園の違いがよくわかりますよ。
転職候補にするかも含めて、ぜひ参考にしてみてくださいね。
目次
幼稚園と保育園~制度や資格の違い

幼稚園の制度や特徴、免許について
幼稚園は、文部科学省が管轄しています。
3歳~小学校入学前の子どもどもたちを、学校教育法に基づいて教育する機関です。
入園に当たって、保護者が働いているかいないかは問いません。
幼稚園との合意ができれば、誰でも入園できるんです。
子どもたちの教育に当たるのは、幼稚園教諭免許を持った教諭です。
幼稚園教諭免許には、幼稚園教諭を養成する教育課程の違いによって、
- 「一種免許状(大学卒)」
- 「二種免許状(短大卒)」
- 「専修免許状(大学院卒)」
の3種類があり、10年ごとに更新する必要があります。
ただ、一種でも二種でも、幼稚園での働き方にほぼ違いはないです。
二種免許状だと園長職にはなれないっていうのと、園によっては給料で差があることもあります。
幼稚園の教育は、「幼稚園教育要領」に基づいて行われます。
各園独自の教育方針も取り入れながら、指導計画を立てて行いますね。
幼稚園の教育時間は、4時間を標準時間としています。
でも、実情としては、9:00~14:00くらいの5時間程度預かる園が多いです。
対象年齢は3歳児~就学前まで。
学年ごとにクラスを分けて、その年代ごとの発達を促すような教育活動をします。
幼稚園によっては、朝と夕方に預かり保育を実施していることがあります。
また、通園バスに幼稚園教諭が添乗することも。
こんな感じの勤務だと、幼稚園教諭の拘束時間は意外に長いかもです。
その他の仕事としては、
- 今日の反省会や明日の指導案作成と活動準備
- 行事に向けての準備と製作
- 保護者対応
- 事務作業
- 清掃
など、さまざまですね。
また、月に数回2歳児を集めて、「プレ幼稚園」をする園もあります。
入園前の親子の遊び場を提供しているわけですね。
一方、公立幼稚園だと、幼稚園教諭は地方公務員の職員となります。
そのため、私立幼稚園の幼稚園教諭の給料や待遇や働き方とは少し違ってきます。
公立幼稚園の場合、初任給は安くても、長く務めれば確実に昇給していきます。
もちろん、福利厚生も充実。
なので、ほとんどの幼稚園教諭が、産休や育休を取って仕事をずっと続けているんですね。
公立幼稚園にベテランの先生が多いのはこのためです。
また、通園バスがなかったり、預かり保育もそこまで拡大していなかったりします。
なので、労働時間もそれほど長時間にはなりません。
保育園の制度や特徴、資格について
保育園は、厚生労働省が管轄。
0~就学前の子どもたちを児童福祉法に基づいて保育する児童福祉施設です。
保育園は、保護者が就労しているなどの理由で、保育に欠けるこどもを預かり保育します。
子どもたちの保育に当たるのは、保育士資格を持った保育士です。
保育士資格は国家資格で、更新などの手続きは必要ありません。
保育園の保育は、厚生労働省の定めた、「保育所保育指針」をもとにしています。
各園の保育方針も加えながら指導計画を作成して行われます。
保育園の保育時間は施設によってさまざま。
基本的には11時間保育ですが、早朝や夜間の保育を行い長時間開園している施設もあります。
保育園では0歳児~5歳児まで幅広い年齢層の子どもたちを預かります。
年齢別保育や、異年齢合同保育など各園で考えた保育形態をとっています。
基本的生活習慣の自立から、各年齢ごとの発達を見据えた活動を取り入れています。
保育園も、公立保育園だとそこで働く正規は地方公務員の職員。
私立保育園の保育士とは、給料や待遇や働き方がだいぶ違ってきます。
初任給は安くても勤続年数が長くなれば、その分昇給するので給料は上がっていきます。
また、産休や育休は、「取るのが当たり前」ぐらいに定着しています。
なので、辞めずに働く保育士は多いです。
だから公立保育園もベテランの保育士が多いんですね。
幼稚園と保育園の違い

幼稚園と保育園の違いを表にしてみましたのでご覧くださいね。↓
| 幼稚園 | 保育園 | |
| 管轄 | 文部科学省 | 厚生労働省 |
| 必要な免許/資格 | 幼稚園教諭免許状 | 保育士資格 |
| 運営目的 | 子どもの教育機関 | 保育に欠ける子どもを預かり保育する |
| 教育/保育課程の基準 | 幼稚園教育要領 | 保育所保育指針 |
| 免許/資格で働ける施設 | 幼稚園 | 保育園、乳児院、児童養護施設、児童発達支援施設など |
| 保護者の就業 | 保護者の就業は問わない | 保護者が就業している |
| 預かる子どもの年齢 | 満3歳~就学前まで | 0歳児~就学前まで |
| 預かり時間 | 標準時間は4時間だが、園によっては朝や夕方に預かり保育を実施している。 | 基本は11時間保育だが、園によっては早朝、夜間も保育を行う。 |
| 休園日 | 夏休み、冬休み、春休み | 年末年始(日数は園による) |
| 人員配置基準 | 1学級:35人につき専任教諭1人 | 0歳児:3人
1、2歳児:6人 3歳児:20人 4、5歳児:30人 につき1人 |
| 勤務体制 | 基本、固定制勤務だが、預かり保育のためにシフト制の園もある。 | シフト制勤務 |
| 教育/保育内容 | 英語、楽器、体操、サッカー、スイミングなどを取り入れていることが多い | 園による。英語や体操などを取り入れている園もある |
| 行事 | 多い | 園による。多い園もある |
幼稚園と保育園は、
- 「幼稚園は教育機関」
- 「保育園は保育に欠ける子どもの保育施設」
ということで、目的はハッキリと違いますね。
でも、両方とも「子どもの健やかな発達を促す」という志は同じかなと思いますよ。
また、幼稚園でも保護者のニーズに応えて「預かり保育」を行っています。
保育園でも英語や体操などの教育的カリキュラムを行っています。
つまり、お互いの要素を取り入れている傾向があるんですね。
なので、「幼稚園だから~」「保育園だから~」と一口には言えないように感じます。
幼稚園の1日の流れと保育園との違い
それでは、幼稚園の1日の流れと保育園との違いについて見ていきましょう。
ただし、時間帯や行っている教育形態、預かり保育の内容などは、園によって違います。
以下の流れは一例だと思ってみてくださいね。
【朝】登園~自由遊び

■幼稚園の場合
幼稚園教諭は、通常勤務であれば、8:00くらいには出勤します。
通園バスに添乗する当番の教諭は、バスの出発時間に合わせてもっと早く出勤することもあります。
また、園によっては「預かり保育」をしており、朝7:00ぐらいから子どもを預かる園も。
早出以外の教諭は、全員で朝の点呼をしてから各保育室に入り、子どもたちの受け入れ準備をします。
9:00くらいになると、徒歩通園の子どもたちが保護者と一緒に登園してきます。
通園バスを利用する子どもは、7:30~10:00くらいの間で順次園に到着。
バス当番の幼稚園教諭は、バス停で子どもを保護者から預かってバスに乗せます。
保護者からの連絡事項があれば聞き取り、バスが走行中には車内の子どもたちを見守ります。
また、園で子どもの受け入れをする幼稚園教諭は、
- 登園後の子どもたちのお支度を促す
- 連絡帳や家庭からの提出物をチェック
しながら、全員がそろうまで、子どもたちの自由遊びを見守ります。
■保育園の場合
保育園では、早番で登園する子は7:00ごろからやってきます。
8:30には普通番の保育士がそろうので、子どもたちは自分のクラスの部屋に移ります。
そして、朝の支度をしてから自由遊びをします。
保育士も、順次登園してくる子どもたちを受け入れていきます。
みんながそろうまで、連絡帳を見たり自由遊びを見守ったりしていますね。
ただ、保育園には送迎バスがないので、バスの添乗がありません。
【午前中】主活動

■幼稚園の場合
子どもたちがそろうと、朝の会をしてから午前中の主活動に入ります。
幼稚園では、音楽、製作、学習、運動、集団活動、などの教育活動を行います。
それは、ほぼ園内の活動です。
園外保育となると、それはまた新たなねらいと計画が必要になります。
なので、公園に出かけることはそんなに多くはありません。
■保育園の場合
一方、保育園は結構頻繁に園外に出かけますよね。
園庭がない保育園は当然なんですが、園庭がある保育園でも散歩に行くのは普通。
子どもたちを思い切り遊ばせるために、しょっちゅう公園に出かけます。
保育園であっても、講師による
- リトミック
- 体操教室
- 英語
などのカリキュラムを取り入れる園は多いです。
幼稚園に似た主活動をしているところも増えてきています。
【お昼】昼食

■幼稚園の場合
お昼の時間になると、幼稚園では基本お弁当ですね。
園によっては、週に2回ほどは給食を取り寄せているところもあります。
■保育園の場合
保育園は全員が毎日給食を食べます。
子どもたちの食事の面倒を見るのは、幼稚園教諭も保育士も同じですね。
食べるのが遅い子を介助したり、お弁当箱や食器の片付けを促したり手伝ったりします。
【午後】自由遊び、お支度、降園

■幼稚園の場合
食事の時間が終わると、幼稚園では、14:00の降園時間まで子どもたちは自由遊び。
幼稚園教諭は子どもたちを見守ったり、遊びに関わったりします。
また、連絡帳を記入しお手紙を配り、帰りの支度をさせて帰りの会をします。
14:00になると、徒歩で降園する子は保護者と一緒に帰りますね。
バスで降園する子は、自分の乗るバスの時間に合わせて順次バスで帰ります。
バス当番の教諭はバスに添乗し、園に残る教諭は園にお迎えに来た保護者に子どもを引き渡します。
■保育園の場合
保育園では給食終了後、お昼寝に入ります。
子どもたちを寝かしつけてからも、保育士にはさまざまな仕事が待っています。
日誌や連絡帳記入や打ち合わせなど、休憩も取れないほど忙しく仕事をしてますよね。
【降園後】預かり保育

■幼稚園の場合
降園時間以降は、幼稚園によりますが預かり保育を実施することもあります。
延長時間は幼稚園ごとに違いますが、大体16:00までとか、19:00までとか、ですね。
預かり保育は、幼稚園教諭が交代で行う園もあれば、専任の職員を雇っている園もあります。
また、預かり保育を英語や体操、サッカーなど、講師による習い事の時間にしている園も。
その場合、幼稚園教諭は預かり保育にはノータッチ。
なので、
- 今日の反省会やその他の会議に参加
- 明日の指導案作成や活動準備
- 行事のための製作や準備
- 保護者対応
- 環境整備や清掃
など、さまざまな仕事をすることになります。
バス当番を終えた教諭も、同じく仕事に戻ります。
通常勤務であれば、17:00ごろが定時ですね。
ですが、この時間で帰れることはほとんどなく、残業があります。
■保育園の場合
保育園では、お昼寝が終わった子どもたちはおやつを食べます。
そのあと、自由遊びをしながら保護者のお迎えを待ちます。
早い場合は16:00過ぎくらいからお迎えが来始めて、順次降園していきます。
17:00以降になると、異年齢児が合同となって遅番保育。
さらにもっとお迎えが遅い子どもは延長保育になります。
普通番の保育士は、遅番保育士に子どもたちを引き渡して1日の勤務は終了。
…なんですが、もちろん仕事が終わらないため残業しますよね。
延長保育は、19:00~20:00くらいまでのところが多いですね。
幼稚園教諭と保育士、給料はどっちが高い?

それでは肝心な、「幼稚園教諭と保育士の給料はどっちが高いのか?」を見ていきましょう。
「令和5年度 賃金構造基本統計調査」によると、
幼稚園教諭(20~24歳)の場合、
| 月収 | 22万6,000円 |
| ボーナス | 49万3,400円 |
| 年収 | 320万5,400円 |
となっていて、
保育士(20~24歳)の場合は、
| 月収 | 23万900円 |
| ボーナス | 43万8,000円 |
| 年収 | 320万8,800円 |
となっていました。
こう見ると、保育士も幼稚園教諭もそう変わらないですね。
幼稚園教諭として働くメリット、デメリットとは?
ここでは、幼稚園教諭として働くときのメリットとデメリットについてお伝えしますね。
幼稚園教諭として働く3つのメリット
まずは、メリットから。
- 子どもと接する時間が短い分、緊張する時間も短い
- 通園バスがあると保護者と会う機会が少ないので、気を遣うことも少ない
- 夏休み、冬休み、春休みなどの長期休みがある
■子どもと接する時間が短いので緊張する時間も短い

まず、幼稚園は標準の教育時間は4時間。
「子どもと接する時間が短いので、緊張する時間も短い」です。
保育園なんかは、早朝から夜までずーっと子どもと一緒です。
保育士は気が休まることがないですよね。
それを考えると幼稚園って、「緊張する時間が短くていいな」と思いますよね。
ただ、園によっては預かり保育もあって、それを幼稚園教諭自身が行うことも。
そうなると、長時間子どもと接することになってしまいますね。
■保護者対応で気を遣う場面が少ない

2つ目に、通園バスがあると保護者が園に来ることがあまりありません。
つまり、「保護者対応で気を遣う場面も少ない」ということです。
保育園でもそうですが、保護者と接するのって、緊張するし気を遣いますよね。
気むずかしい保護者や、くせのある保護者などは、余計にそう。
対応しずらいし、顔を会わせると思うと気が重いです。
でも、通園バスで登園してくる子が多い幼稚園なら、その心配はだいぶ少ないかもしれませんね。
■夏休み、冬休み、春休みなどの長期休みがある
3つ目に、「夏休み、冬休み、春休みなどの長期休みがある」ということです。
これは、保育園にはないものですよね。
保育園で1番長い休みは、年末年始休みの5~6日間くらいですかね。
ただ実際には、夏休みといえども、
- 夏季保育
- お泊り保育
- 夏祭り
などの行事があったり、普段できない
- 残務整理
- 研修
- 飼育している動物の世話
のために飛び石で数日は出勤したりもします。
つまり、「まるまる40日間お休み!」ということはなわけです。
多くて20日間くらいですかね。
でも、園によってはもっと少ないところもあるんです。
まあ、普段から長時間残業や持ち帰り仕事が多いですからね。
「20日間くらいまとまって休んでもまだまだ足りない!」といったところでしょうか。
こんな感じで、幼稚園には長期休みがあってもすべてが休みじゃないんですね。
幼稚園教諭として働くの4つのデメリット
では、続いてデメリットを見てみましょう。
それは、
- 長時間の残業と持ち帰り仕事が多い
- 保護者と接する時間が少ないので信頼関係が築きにくい
- 保護者同士のトラブルが多い
- 「教育」なので、保護者からのプレッシャーが重い
■長時間の残業と持ち帰り仕事が多い
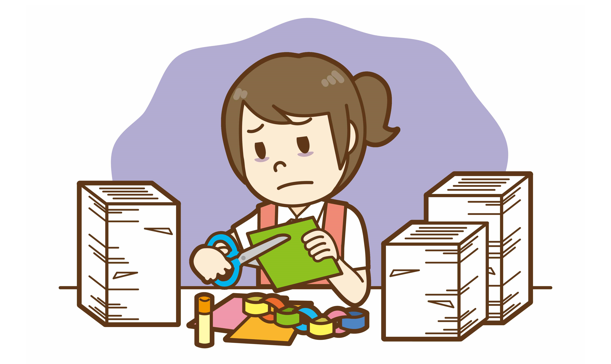
まず、「長時間残業と持ち帰り仕事が多い」ということですね。
- 「幼稚園は、子どもが早く帰るでしょ?」
- 「夏休みとか長期休みがあるじゃない?」
何て思ったら大間違いなんです。
幼稚園教諭の仕事は終わりがないんです。
たとえば、
- 連絡帳の記入
- おたよりなどの書類作成
- お誕生日カード作り
- 壁面製作
- 行事やその他の会議
- ピアノの練習
- 活動の下準備
…など山のように仕事があるんです。
私の知り合いの幼稚園教諭も言ってました。
「持ち帰り仕事をしながら寝てしまって、夜中に起きてまた仕事して、朝になって出勤…」なんてこともよくあるそうです。
それで、体を壊して辞めていく幼稚園教諭も後を絶たないとか。
これでは、保育士に負けず劣らずな大変さですよね。
■保護者と接する時間が少ないので信頼関係を築きにくい

2つ目は、「保護者と接する時間が少ないので信頼関係が築きにくい」こと。
さきほど、「保護者と顔を合わせなくて済む」とメリットのところで言いました。
でも、その裏にはこういったデメリットがあるんですね。
確かに、保護者と合わなければ顔も覚えられませんし。
連絡帳くらいでしかコミュニケーションが取れないですよね。
保護者のことがよくわからない状態で、何かネガティブな報告をするって、すごく言いづらい。
保護者だって、「幼稚園の先生から連絡が来るのは、何か問題があるとき」なんて思ってます。
その点、保育園はほぼ毎日保護者と会うので、顔はわかるし、雰囲気もわかります。
まあ、早番や遅番を利用していて、担任と会うチャンスが少ない保護者もいますけど。
でもいずれ、保護者のカラーはわかってきます。
保護者と話すのってもちろん気を遣うこと。
ですが、そういったコミュニケーションの積み重ねで信頼関係はできていきます。
その信頼関係があるから、何かあった時にも話ができるんですよね。
■保護者同士のトラブルが多い
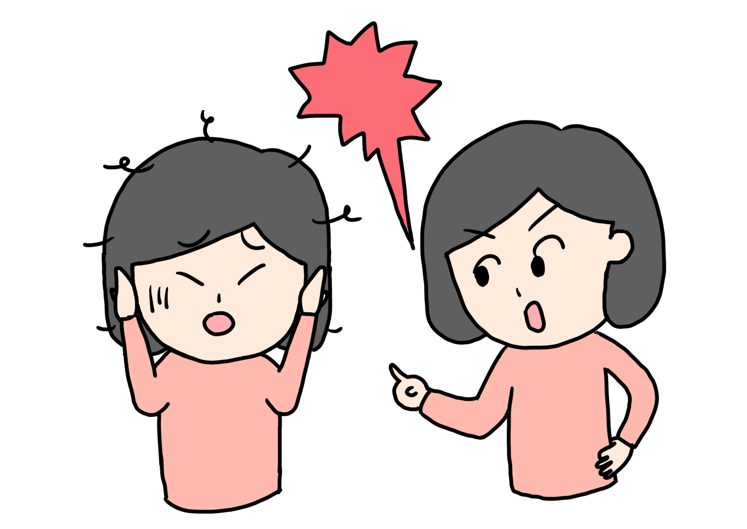
3つ目は、「保護者同士のトラブルが多い」ですね。
幼稚園に子どもを通わせている保護者は、働いていない方が多いです。
そうすると、子どもを登園させた後に
- 保護者同士で立ち話
- 係活動で保護者が園に集まる
といった時間が結構あります。
そこで、保護者同士のトラブルが発生しやすいんですね。
でも、保護者トラブルがあることを訴えられても、幼稚園としては困っちゃいます。
保護者同士のことの間に入って取りなす、なんて難しいです。
そこへいくと、保育園の保護者は、みんな働いています。
朝はいつも急いでいて、「預けたらパッと仕事に行く」という感じ。
帰りも子どもを追い立ててサッサと帰る保護者は多いです。
(まあ、中にはモタモタしている方もいますが…)
そんな感じで、保護者同士で接する時間が少ないので、トラブルは起こりにくいです。
■「教育」なので、保護者からのプレッシャーが重い
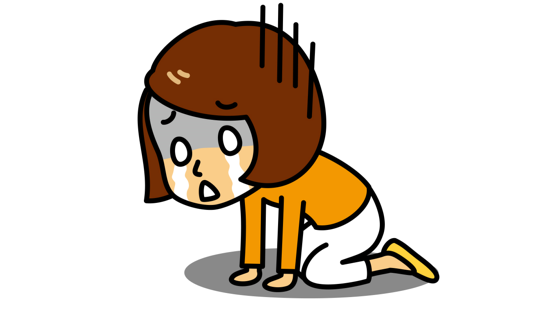
4つ目は、幼稚園は「教育」なので、「保護者からのプレッシャーが重い」ということ。
保護者は、幼稚園で行う「教育」にさまざまな期待を寄せているからです。
たとえば、
- 「ピアニカができるようになってほしい」
- 「いろいろな運動を経験させてほしい」
- 「絵や工作が上手になってほしい」
- 「英語ができるようになってほしい」
- 「運動会や発表会は高度で立派なもの見せてほしい」
などです。
こんなふうに、幼稚園には何かしらの教育の成果を求めていることが多いです。
これは、幼稚園教諭にとってはプレッシャーですよね。
だって、頑張って指導して成果が出ても、「できて当然」。
成果が出ないと、「なんでできないの?!」という目で評価されてしまうから。
それに比べて、保育園ではそこまで保護者の目は厳しくないです。
「毎日我が子を安全に預かってもらう」ことの方が大事だったりします。
なので、運動会や発表会の成果がどう、とか、そこまで気にしていないのでは? と思います。
もちろん、保育士としては全力を尽くして行事に当たりますよ。
それなりにプレッシャーも感じていますしね。
…こう見てくると、幼稚園教諭として働く時のメリットは確かにあります。
ですが、それは裏を返せばデメリットにもなります。
なので、どうとらえたらいいのかは難しいですね。
また、保育園と同じくらい膨大な仕事があったり、保育園にはない独特な大変さもあります。
そう思うと、「幼稚園の方が楽」とは一概には言えないかも、ですね。
幼稚園も保育園も互いの機能が近寄ってきている

幼稚園と保育園の特徴を見てくると、お互いの機能が近寄ってきているようにも見えますね。
たとえば、
- 幼稚園では、「預かり保育」が行われている
- 保育園では、「教育的プログラム」を取り入れている
というようなところですね。
もちろん「幼稚園は教育活動の場」であり、「保育園は生活支援の場」といった住み分けはあります。
ですが、「子どもたちをより健康に心豊かに育てていきたい」という共通の願いがあります。
そして、より保護者のニーズに応えていこうとしています。
だからこそ、幼稚園は保育園らしさを、保育園は幼稚園らしさを取り入れているんだと思います。
基本的な制度や細かいところで違いはあります。
が、現場の実情としては、幼稚園や保育園の区分けはしにくくなっているのかもしれません。
最近は、幼稚園でも保育園でも、園それぞれが個性を打ち出してきていますよね。
と思うと、
- 「その園(幼稚園/保育園)がどんな方針を持つのか」
- 「どんな働き方になるのか」
に注目することの方が大事なのかもしれませんね。
まとめ

幼稚園のこと、イメージできましたか?
- 「子どもが早く帰るから楽そう」
- 「夏休みがあっていいな」
なんて思っていた方も、「そうでもないのか~」なんて感じたかもしれないですね。
幼稚園、保育園というカテゴリーを理解しつつ、
- 「その園(幼稚園/保育園)がどんな方針なのか」
- 「どんな働き方ができるのか」
に注目しましょう。
各施設の様子や働き方を詳しく知りたい場合は、ホームページは要チェック。
そして、保育士転職サイトに聞いてみるのがいいと思います。
求人を扱っている幼稚園や保育園のことは、ちゃんとリサーチしています。
なので、詳しく教えてもらえますよ。
あなたが自分らしさを発揮できるのはどちらの職場なのかを考えてみてくださいね。
またその園ならではの特徴や働きやすさを見極めて、じっくりと検討しましょう。