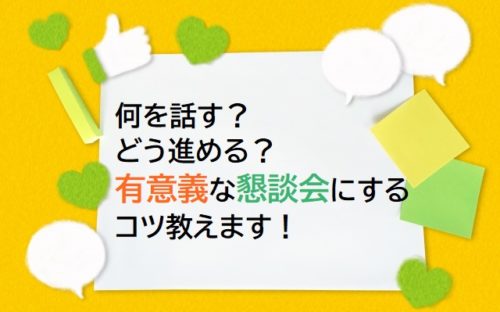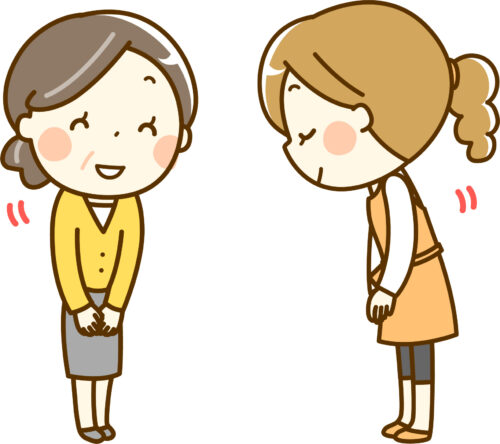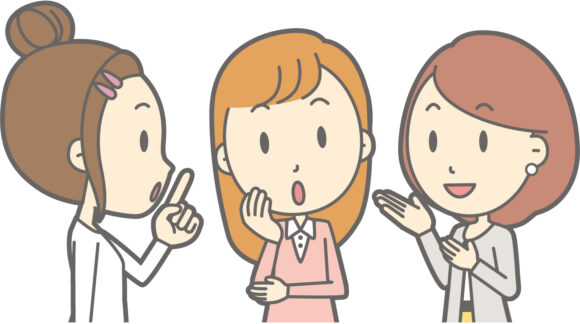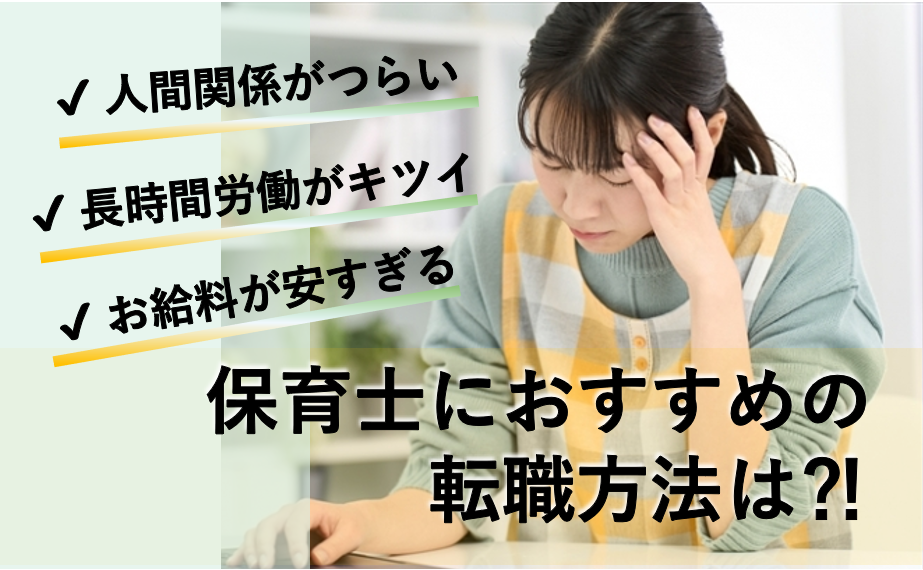こんにちは! 現役保育士はなえみです(転職でホワイト園に巡り会えました!→ プロフィールはこちら)。
あなたの園でも懇談会ってありますよね。
懇談会には、わざわざ仕事を休んで保護者の方が集まってくれています。
なので、有意義な話ができて、「参加してよかった!」と思ってもらいたいですよね。
でも、
- 「どんな内容にしたらいいかな…?」
- 「盛り上がらなかったらどうしよう」
- 「大勢の保護者の前で話すのが苦手で…」
って、いつも悩んでしまうと思います。
今回は、「懇談会を成功させるおススメの内容と進行のコツ」についてお伝えします。
懇談会への不安や悩みを解決できて、自信を持って当日を迎えられますよ。
- 記事の信頼性
- 私自身、30年以上の保育士経験があります
- 0~5歳児のクラス担任を経験し、何度も懇談会を企画、開催してきました
- 懇談会で取り入れたい内容やどんなテーマが盛り上がるのか熟知しています
私の経験をフルに盛り込んでいるので、ぜひ参考にしてくださいね。
目次
そもそも懇談会の目的とは?
まずは、懇談会の目的を再確認してみましょう。
それは下の3つ。↓
- 園の運営やクラス運営について知ってもらう
- 子どもたちの生活や遊びの様子、成長した姿を知ってもらう
- 保護者同士で子育ての悩みを共有し、親睦を深める
まず、「園の運営やクラス運営について知ってもらう場」ということですね。
特に入園後、または進級後の初めての懇談会の場合は、
- 「園長はどんな考えを持ってるのか」
- 「担任はどんなふうに子どもたちを成長させたいのか」
って、ことをしっかり伝えたい。
担任が語ることで、どんなキャラクターなのかも知ってもらえます。
2つ目としては、「子どもたちの生活や遊びの様子、成長した姿を知ってもらう」ですね。
たとえば、年度初めの懇談会であれば、
- 入園や進級してから今日までの子どもたちの変化
- 今の子どもたちが楽しんでいる遊びの様子
などを伝えます。
もし、年度終わりの懇談会であれば、
- 1年間を振り返って成長した姿
を伝えられますよね。
保護者の方は、わが子がどんなふうに園で過ごしているのかが一番知りたいもの。
なので、リアルな姿を伝えてあげましょう。
最後に、「保護者同士で子育ての悩みを共有し、親睦を深める場」ということです。
保育園は送迎時間がバラバラなので、保護者同士が顔を合わせる機会が少ないです。
顔を合わせたとしても、たまたま送迎時間が同じ保護者に限られる。
なので、保護者同士が広く知り合うチャンスって少ないんですね。
ですが、懇談会に参加すれば、いつも顔を会わせない保護者と会えます。
そして懇談会を通して仲良くなることも。
また、育児の疑問やお悩みを話し共有することで、気持ちが軽くなることも。
育児以外の情報交換もすればお互いに親近感がわき、より親睦が深まりますよね。
この3点は、懇談会を行う大事な目的。
会の内容にしっかり盛り込んでいきましょう。
【セリフ付き】おススメの懇談会の進め方!
まずは、「懇談会の流れ」を紹介しましょう。↓
- 始まりの言葉、会の流れの説明
- 園長、担任からの挨拶
- 保護者の方から一言ずつ(アイスブレイク)
- クラス目標と年間保育計画
- 最近の子どもたちの様子
- ご協力のお願い
- 保護者同士の交流タイム
- 終わりの言葉
年度終わりの懇談会の場合は、「クラス目標」「年間保育計画」は入れないと思います。
そして、あなたの園の方針やあなたの考え、また開催時期によって内容は変えてくださいね。
では、具体的なセリフありの、「おススメの懇談会の進め方」に入っていきましょう。
①始まりの言葉と園長、担任からの挨拶
まずは、担任から始まりの言葉を言います。
- 「本日はお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます」
というようなことを言いましょう。
保護者の方が仕事で忙しい中、時間を作って参加してくれたことに、感謝の気持ちを表しましょう。
その後、引き続き挨拶をします。年度初めなら、今年度の抱負や意欲を話すとよいですね。
たとえば、その時のセリフはこんな感じで。↓
といったような感じですね。
逆に、年度終わりの懇談会であれば、
という感じでしょうか。
続いて、園長から一言挨拶をもらいます。この時の内容は園長先生にお任せしてもいいでしょう。
ただ、保護者へのお願いなど、内容によっては園長からしっかりと伝えてもらった方がいいこともあるので、それはあらかじめお願いしておく必要がありますね。
② 保護者の方から一言ずつ(アイスブレイク)
次に行うのが、保護者の方から一人一言ずつもらっての「アイスブレイク」。
アイスブレイクとは、直訳で「氷を壊す」。
つまり、緊張した空気を解かすように簡単な会話やゲームをして和ませること。
そうすることで、参加者がリラックスして会に参加できるようになるんですよね。
私は、いつも何かお題を出して、それに沿って保護者の方から一言ずつ話してもらっていました。
たとえば、
みたいな感じですね。
これで、保護者の方の内面が見えて、場が和むんですよね。
でも、この時のお題を何にするかも悩みますよね。
たとえば、
- 最近面白かったこと
- 最近イラっとしたこと
- 最近失敗したこと
- うちの子のかわいいところ
- うちの子の困っているところ
- 子どもの名前の由来
- 「実は…私こう見えて○○なんです」
なんてことをテーマにするのもいいですね。
子どものことだけでなく、自分自身のことを話すのも、保護者の方は楽しいと思いますよ。
③クラス目標と年間保育計画
アイスブレイクを兼ねた自己紹介が終わったら、担任からの話をします。
年度初めであれば、クラス目標と年間保育計画を話すといいでしょう。
たとえば、3歳児クラス目標を話すとしたら、こんなセリフはどうかな、と。↓
「今年度の○○ぐみさんのクラス目標は3つのことを掲げてみました。
一つ目は、『全身を使った遊びをのびのびと楽しむ』です。3歳児さんは動きがさらに活発になってくる時期なので、体を動かして遊ぶ環境をしっかりと整えたいと思います。
二つ目は『さまざまな遊びを通して興味や関心を広げていく』です。好きな遊びを十分に楽しみながらも、新たな遊びを提案したり、誘ったりしながら、新たな発見や驚きを共有していきたいと思います。
三つめは、『友だちと関わりながら楽しく遊ぶ』です。まだまだこの年代は自分が中心になりがちです。でも、保育士が仲立ちになって相手の思いを伝えたり、どうしたら仲良く遊べるかを一緒に考えたりしながら、友だちとの関わりを深めていきたいと思います」
これに、もっと言葉を足してもいいですし、あなたのクラスの目標に合わせてアレンジしても。
大事なのは、クラス担任として、
- 「どんなクラス運営をしようとしているのか」
- 「何を大切にして子どもたちを導こうとしているのか」
を伝えることですね。
さらに、年間保育計画として、いつどんな活動や行事があるのかを伝えましょう。
たとえば、
といった感じでさらっと、「いつ、何をするのか」をシンプルに伝えればよいと思います。
できれば、わかる範囲で少し説明を足してあげるといいですね。
たとえば、
みたいな感じですね。
④ 最近の子どもたちの様子
続いては、最近の子どもたちの様子を伝えます。
年度初めの懇談会で6月ごろに行うなら、4月から今までの子どもたちの変化を話しましょう。
4月から今までの日誌を読み返してみると、いろいろと思い出せるかも。
そして、何を話すかを整理していきましょう。
話すポイントとしては、
- 生活(食事、排せつ、着脱)
- 遊び(自由遊びと集団遊び)
- 友だちとの関わり
- 行事への取り組み
などに項目わけして内容を整理すると、話しやすいし伝わりやすいと思いますよ。
たとえば、新年度の懇談会の場合、3歳児クラスの様子の冒頭はこんな感じでしょうか。↓
そして、「生活」「遊び」「友だちとの関り」「行事」について、紹介してみましょう。
一方、年度末の懇談会なら、1月か2月ごろでしょうか。
その場合は、1年間の生活や行事を振り返って、成長したことを話すのがいいですね。
このときも、さっきと同じように内容を整理し、「こんなふうに成長しました」と話せばOK。
たとえば、動画や写真を取っておいてそれを見せながら解説すると、よりリアルに伝わりますね。
保護者の方も、画面の中にわが子が少しでも映っているとうれしいもの。
「けっこう楽しそうに過ごしているな」「うちの子もがんばっているんだな」って感じられます。
できそうであれば、やってみるのもおすすめですよ。
⑤ご協力のお願い
ご家庭の協力が必要なことがあれば、お願いをしておきます。
1年間を通して変わらないお願いごとであれば、この機会にしておきましょう。
たとえば、
- 「熱が37.5度以上ある場合は登園を控えてください」
- 「持ち物には名前を書いてください」
- 「爪を切ってきてください」
- 「送迎時にはお子さんから目を離さず、車の往来に注意してください」
などですね。
このとき大事なのは、「どうしてそれが必要なのか」についても説明すること。
そうすると、お願いごとの意図が伝わるので、協力してもらいやすいです。
懇談会は多くの保護者の方に、一斉にお願いやお知らせがしやすい貴重な機会。
なので、ぜひ活用しましょう。
他には、今後の生活や活動で必要になる物、行事で使う物について予告するのもいいですね。
ただ、あんまり先の行事について予告しても忘れちゃいます。
なので、直近のことについてだけ、お願いしましょう。
⑥保護者同士の交流タイム
ここからは保護者同士の交流タイムになります。
この時間をどうするか、これもいつも悩みますよね。
でも、その目的は保護者同士の交流を深めることですよね。
保護者の方って、他の保護者の悩みや考えていることを聞いてみたいもの。
その一方で、自分もしゃべりたいはずなんです。
この会がきっかけとなって保護者同士が知り合い、交流が広がるといいですよね。
そこでよくやるのが、少人数のグループに分けて、テーマに沿った話を自由にしてもらうこと。
私はいつもそんな感じでやっていました。
私が懇談会で取り上げてきたテーマはこんな感じです。↓
- 子どもの食事の悩み
- トイレットトレーニングの悩み
- イヤイヤ期の悩み
- おススメのお出かけスポット
- 家事の時短テクニック
- 私のストレス解消法
テーマを考えるコツは、「誰でも経験していて、話せる内容がある話題にすること」です。
上にあげたテーマは誰もが悩みそうだったり、経験していそうなことだったりしますよね。
という感じで、交流タイムに向けては、このようなテーマを一つ決めておきます。
そして、くじ引きなどで3~4人のグループを作りましょう。
そして、書記と発表者を決めてもらってから、話し合いのスタートです。
このとき大切なのは、各グループでどんな話をしているか、担任が順番に回って様子を見ること。
もし「話が進んでないな」と思ったら、少しそのグループに入ってみて、担任から話を振ってみましょう。
そして、交流タイムの最後には、各グループで出た話を全体に発表してもらいシェアします。
そうすると、「へー、そんな話が出たんだ」と保護者の皆さんも楽しそうに聞いてますよ。
⑦終わりの言葉
交流タイムが終わると、懇談会もこれで終了です。担任から終わりの言葉を言いましょう。
終わりの言葉はシンプルでいいと思います。
たとえば、
といった感じです。
もし、年度末の懇談会の場合は、
といった感じでよいでしょう。
解散前にアンケートを配って、今日の感想を寄せてもらうのもおススメです。
参加した保護者の方の満足度を知っておくと、今後の参考になるでしょう。
「今後取り上げて欲しいテーマ」を書いてもらうというのも、次回を考えるときの参考になりますね。
もちろん、懇談会は今回紹介したような形だけではないと思います。
園によって内容や流れ、進め方は違うかと思いますし。
なので、取り入れられそうなところがあれば取り入れてみたり、アレンジしたりしてくださいね。
懇談会の進行の3つのポイントは?
それでは、懇談会の進行のポイント3つをお伝えしますね。
それは、
- 時間配分を決めておき、調整しながら進める
- 誰もが一言は話せるように配慮する
- わからないことは即答しない
の3つですね。
時間配分を決めておき、調整しながら進める
これは、限られた貴重な時間を有効に使うためにはとても大事なこと。
なので、それぞれの内容に何分ずつ使うのか、配分をざっくりと決めておきましょう。
担任として話す内容もあらかた決めておいて、どのぐらい時間がかかるのか計っておくのもいいです。
また、時間が押してきたときのために、カットする部分を決めておくとその場で調整しやすいですよ。
ちなみに、自己紹介のとき、一人で長くしゃべってしまう保護者っていますよね。
それが心配なら、
- 「今日の自己紹介はお一人1分でーす!タイマーが鳴ったら次の方に移りますのでよろしくおねがいしまーす!」
と決めてしまいましょう。
そうすれば、どれぐらい話せばいいのか保護者の方にもわかりやすいですよね。
話しが長くなったら途中で切られることもある、という予告にもなります。
そうすることで、時間管理がうまくできるようになりますよ。
誰もが一言は話せるように配慮する
全体を見渡して、意見を言っていない人にも発言を振るようにしましょう。
これは、クラス担任が司会をする時の重要な役割です。
一見大人しくて話しベタなように見えて、でも話を振ると意外に話が上手な保護者もいます。
自分なりの意見をしっかり言えるんですよね。
なので、
- 「それでは、○○さんのおうちではどんな感じですか?」
- 「○○さんも、確かお兄ちゃんがいらっしゃいますよね。おうちではケンカします?」
- 「○○さんも、□□ちゃんがなかなか園に慣れなくて、心配されていましたよね?」
なんて、一人一人の思いを引き出してみましょう。
グループトークがシーンとしている時や、一人だけがしゃべっているようなら、担任の出番。
こんなふうにちょっと振るだけで、保護者の方も安心して話し始めますよ。
答えに困ること、わからないことは即答しない
懇談会中に保護者から質問されても、答えに迷ったりわからなかったりすること、ありますよね。
そんなときは、
- 「あとで調べてお答えしますね」
- 「園長に相談しますね」
と、答えを保留しましょう。
懇談会では大勢の保護者にいっぺんに伝わってしまうので。
間違いだったとき、後から訂正するのもタイヘンですからね。
「わからなかったら即答しない」で全く問題ないです。
相談できる人に聞いてから、正しい答えを返すようにしましょう。
懇談会前にするべき3つの準備
懇談会の前に準備しておく3つのこととは何でしょうか。
それは、
- 子どもの様子を観察する、子どもの言葉をメモしておく
- レジュメづくり
- アンケートを取り、話したいこと聞きたいことを聞いてみる
ですね。
子どもの様子を観察し、子どもの言葉をメモしておく
普段の様子を具体的に伝えられるよう、子どもたちの遊びや言葉を観察し、メモしておくといいです。
「誰と誰がよくこれで遊んでいるな」とか、「こんなことができるようになってる」とか。
それに、思わず笑ってしまう子どものかわいい言葉とか。
そういったことを伝えると、保護者は楽しく聞いてくれますよ。
なので、「あ、これ面白いな」「これ、伝えたいな」ということを、ササっとメモしておくといいですよ。
「先生、よく見てくれているんだな」なんて、保護者の方もきっと安心しますよ。
レジュメづくり
レジュメには、「保護者に読み返してほしいこと」を載せるとよいです。
たとえば、
- 本日の流れ
- クラス目標
- 年間保育計画
- 行事予定
- ご協力のお願い
などですね。
内容は決まっていることなので、書くことはそれほど多くないですね。
ちなみに、年度終わりの懇談会であれば、「クラス目標」や「年間保育計画」「行事予定」はいらないかな。
「子どもたちの様子」も、担任がしゃべるので、あえて書かなくてもいいと思います。
もし書くとしたら、ポイントだけを箇条書きにする感じでいいと思いますよ。
アンケートを取り、話したいこと聞きたいことを聞いてみる
これはやってもやらなくてもいいんですが、「前もってアンケートを取っておく」ということもありかな、と。
懇談会のテーマに悩むなら、アンケートで保護者の方に意見を聞いてみる、ということです。
保護者の方が知りたいこと、話したいことがわかるので、これも一つの方法ですね。
懇談会の出欠席を出してもらう時に、それも一言書いてもらうような形を取れば、アンケートになりますね。
ただ、そのときは園長の許可を取ってからにしましょう。
そして、アンケートは取りっぱなしにならないように、ちゃんと活かしていきましょうね。
まとめ
「そろそろ懇談会のことを考えなきゃ…」って思うと、あれこれと不安が出てきてしまいますよね。
でも、保護者は純粋に、我が子が保育園でどんな風に過ごしているのかが知りたいんです。
なので、あまり構えずに、担任として普段子どもたちをどうとらえているのかを伝えましょう。
また、貴重な時間なので、保護者同士をつなげる楽しいこともできるといいですね。
そこは、この記事で紹介したことを参考にしたり、あなた独自のアイデアを盛り込んでみてくださいね。
大勢の保護者の前で司会進行をするのは、本当にドキドキするものです。
でも、いつも通りの笑顔であなた自身も懇談会を楽しんで、有意義な時間にしてくださいね。