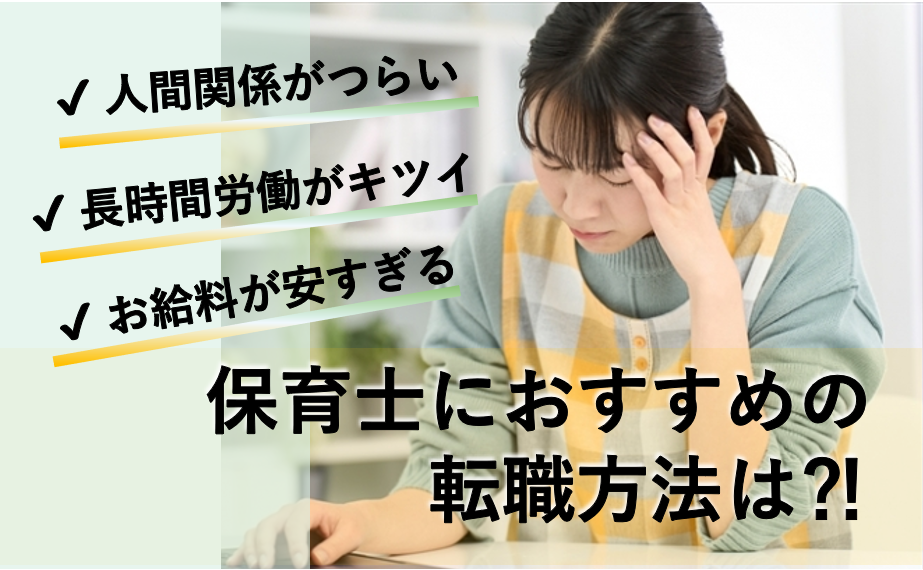こんにちは! 現役保育士はなえみです(転職でホワイト園に巡り会えました!→ プロフィールはこちら)。
「保育士として頑張ってきたけど、もう保育園では働きたくないな」と思う保育士の方もいますよね。
たとえば、
- 「職場の人間関係が悪すぎて、今後良くなる見通しなんてない」
- 「業務が忙しすぎて、子どもとじっくり向き合うことができない」
- 「運動会や発表会は、園長から出来栄えばかりを評価されるので疲れる」
など、自分らしく働けていないことに疑問を感じる保育士の方は多いです。
そうなると、「別の保育園に転職しても、やっぱりまた同じことの繰り返しになるのでは?」なんていう気持ちがわいてくるのもわかります。
ならば、保育士資格を活かして、保育園以外の施設に転職するのはどうでしょうか。
じつは、私も保育園以外の児童福祉施設で働いたことがあるんですよ。
保育園とはまた違った子どもたちを対象とする施設であり、施設の目的も違うので働き方はガラッと変わりました。
そして、私自身の保育士としてのキャリアの幅も、確実に広がったんです。
この記事では、保育園以外の施設に転職してみたい保育士の方に向けて、「保育園以外で保育士資格を活かして働ける児童福祉施設」について詳しく解説します。
また、そのような、「保育園以外の児童福祉施設で働くメリット、デメリット」にも触れています。
保育士資格を活かした、さまざまな施設での働き方を知ることで、転職の可能性をぜひ広げてほしいと思います。
目次
保育士資格を活かして働ける児童福祉施設とは?
児童福祉施設とは、児童福祉法などの法令に基づいて運営され、子どもの安全を守り成長を促すため、さまざまな状態の子どもたちや家族のニーズに沿った支援をする各種施設のことです。
保育園も児童福祉施設に含まれていますよね。
そして、それ以外にも児童福祉施設はいくつかありますし、そのどれもが、保育士が働ける施設なんですよ。
それは以下のようになります。
- 助産施設
- 乳児院
- 母子生活支援施設
- 児童厚生施設(児童遊園・児童館)
- 児童養護施設
- 障害児入所施設
- 児童発達支援センター
- 児童心理治療施設
- 児童自立支援施設
- 児童家庭支援センター
これらの施設は、何かしらの困難を抱えている子どもやその家族が、よりよく生活していくために必要な支援を行っています。
施設ごとに目的や対象が違うため、保育士の働き方もそれなりに変わってはきますが、子どもやその家族に対して真摯に向き合い関わろうとする姿勢は共通です。
保育園から転職した場合でも、園での経験が十分に活かされるはずですし、また保育園に戻って働いたとしても必ず活かされる貴重な経歴になりますよ。
では、一つひとつの施設について見ていきましょう。
助産施設
助産施設とは、出産時に異常をきたす恐れがある妊婦、または、自宅が不衛生で出産の介助者もいない妊婦が、所得が一定以下の低い水準にあり、助産所や病院で入院・分娩ができない場合にその出産を助ける施設のことです。
つまり、通常の妊婦さんに比べて、体調的にも環境的にもリスクが高い妊婦の方が、お金の心配をせずに、安心して出産できるように支援するんですね。
そんな助産施設ですが、実は独立した施設ではなく、一般の助産所や産婦人科病棟の病室の一部をあてていることが一般的です。
あらかじめ助産施設として指定されている助産所や産婦人科病院が、「助産施設が必要」と認められた妊婦を受け入れてケアをします。
なので、助産施設を利用する妊婦は、一般入院している他の妊婦と同じように必要な処置をされることになります。
なので、保育士が、「助産施設で働く」というのは、「産婦人科病棟や助産所で働く」といったこととほぼ同じになるでしょう。
生まれたばかりの赤ちゃんのお世話をしたり、出産後間もない不安でいっぱいのお母さんの話をして聞いてあげたり、育児のアドバイスをしてあげるなどが主な仕事になります。
出典:助産施設 WAM NET
乳児院
乳児院とは、何らかの理由で保護者と一緒に生活できない1歳未満の乳児を保護し預かって育てる施設です。
子どもが乳児院に入所する理由は、保護者が死亡してしまった場合はもちろん、生きていたとしても、病気、離婚、家出、虐待、子ども自身の障害など、さまざまな事情によって保護者による育児ができなくなってしまったためです。
乳児院に入所する子どもの年齢は1歳未満が対象ですが、子どもの事情によっては、2~6歳でも預かることがあります。
保護者の一時的な出産や入院によって預けられる子もいますが、多くは長期的に乳児院で生活します。
そしてその後は、保護者と再び暮らせるようになる子、里親に引き取られる子、児童養護施設(対象年齢1歳~18歳)に移っていく子など、さまざまです。
結局、乳児院は子どもにとって家庭の代わりになる生活の場であり、そこが保育園とは大きく違います。
保育園は、保護者が仕事などで面倒を見られない間だけ保育する場所ですから、預けられていても必ずその日のうちに保護者が迎えに来ますし、生活の基盤は各家庭にあります。
ですが、乳児院はそこが家であり、子どもの唯一の居場所なんです。
保育士やその他の職員は、一人一人の子どもの状態や家庭の背景をふまえた上で、日々ぬくもりある養育をすることで信頼関係を築き、健やかな育ちを促しています。
そんな乳児院の保育士は、当然24時間、365日体制で勤務します。
土日、祝日もシフトが入りますし、夜勤もあります。
そして、保育士以外の看護師、栄養士やその他の専門職もいるので、チームになって対応することになります。
子どもの親代わりとなって身の回りの世話をし、子どもの思いを受け止めながら養育することは、大変だからこそやりがいがあります。
子どもたちの生活の場であることを理解し、乳児期という、子どもがこれから成長していく上で基盤となる大事な時期に関わっていることを自覚しながら業務に当たる必要があります。
母子生活支援施設
母子生活支援施設は、「家計が苦しい」「住むところがない」「夫のDVから逃れたい」など、生活や就労に困っている18歳未満の子どもを持つ母子世帯を受け入れ、生活の場を提供します。
そして、就労支援や生活支援、子育て支援などを行い、ゆくゆくは母親が子どもと共に施設を出て自立していくことを目的とする施設なんです。
施設内には一世帯ごとに独立した部屋が設けられていて、母子それぞれの生活ができるようになっていて、母親は施設から通勤し、子どもも保育園や学校に通います。
施設には、仕事や金銭的なこと、子育てのこと、家族のことなど、母親からのさまざまな相談に対応する職員や、母親が子どもを見られないときは、代わりに子どもの面倒を見たり遊んだり、学習指導をしたりする職員が常駐しています。
具体的には、母子支援員、少年指導員、保育士、支援員、心理療法担当、嘱託医などで、いろいろな職種が連携して支援に当たります。
その中でも保育士は、子どもの面倒を見たり遊んだりすることが主な役割になります。
たとえば、保育園に入れていない乳幼児や、保育園に通っていても、夜間や休日などの時間帯に保育を必要とする子どもを保育します。
それによって、母親が働きやすくなり、金銭的に安定できれば自立した生活につなげられますよね。
また、母子生活支援施設での保育は、母親が仕事のときに限らず、リフレッシュしたいときでも預かります。
精神的にゆとりを持ち楽しんで生活してもらえるようにすることも大切な支援ですからね。
ただ、母子生活支援施設に入所する母親は、誰もが悩みや困った状況を抱えているので、子どももその影響を受けて不安定になっている場合があります。
なので、保育士は、子どもの精神状態にも気を配り、細やかに配慮しながら保育する必要があります。
一般の保育園での保育や保護者対応とは違った気遣いが必要になるのかもしれませんが、「一組一組の母子とじっくりと向き合って信頼関係を作り、自立に向けてのサポートをする」という大きなやりがいがあります。
児童厚生施設(児童遊園・児童館)
児童厚生施設とは、地域の子どもたち(0歳~18歳未満)が健全に遊び成長するための環境を整えている施設のことです。
児童厚生施設には「児童遊園」と「児童館」があります。
児童遊園は、簡単に言うと公園のことですね。
保育園児たちもお散歩に行ってよく遊びますから、保育士にはおなじみの場所ですよね。
一方、児童館は屋内施設で、児童の遊びを指導する施設職員が、子どもたちの遊びが充実するように環境を整えたり、実際に遊びを提供したりします。
たとえば、午前中は未就園児を対象にした、親子で参加するプログラムを行っていることが多いです。
歌やゲーム、おはなし会、工作など子どもたちが楽しく遊べるイベントを企画し、施設職員がリーダーとなって複数の親子に遊びを提供します。
また、児童館では、親のためのプログラムも用意されています。
乳幼児を持つ母親同士で育児や生活のさまざまな情報交換ができる場を提供していたり、講座や教室などを開いて育児の勉強ができる機会を設けたりしています。
午後は、小学生向けのプログラムが中心になります。
日常的には、卓球やドッジボール、一輪車などの運動的な遊びや工作、ゲームなどができ、地域の子どもたちが自由に出入りして遊びに参加し楽しむことができます。
また、月ごとや季節ごとにも特別なイベント(祭りや教室、キャンプなど)を企画し、子どもたちが多様な経験をしながら仲間を作り、思い出作りができるようにしています。
そして、両親が働いている小学生向けには学童保育を行っています。
放課後や夏休みなどの長期休暇には、保護者の代わりに小学生の保育をします。
おやつを食べさせたり学校の宿題を見たり、また、小学生が楽しめる遊びを提供したり、安全に楽しく放課後を過ごせるように、適宜対応したり見守ったりします。
このような児童館で働く職員は、保育士、社会福祉士、教員免許などいずれかの資格が求められることが多いです。
また、上記の資格保持者や、その他の決められた条件を満たしている方は、各都道府県が行っている研修を受けることで、「放課後児童支援員」の資格を得ることができます。
保育園とは違って、児童館で働く場合は、児童館を利用する幅広い対象のニーズに合わせて、創意工夫のある支援が必要になります。
乳幼児の親子や、小学生などの年齢が高い子どもたちへの理解を深め、それぞれの年齢に合った働きかけをしながら、安全に楽しく活動できる場を作ることが大切です。
児童養護施設
児童養護施設とは、親がいない子ども、または、親がいても適切な環境で養育してもらえない子どもを入所させて、親の代わりに子どもを保護し、養育する施設です。
子どもの対象年齢は1歳~18歳となっていますが、事情によっては20歳まで延長することもあります。
児童養護施設に入所する子どもの家庭の背景はさまざまですが、たとえば、父母が行方不明であったり精神疾患があったり、離婚、虐待などは特に多い理由です。
児童養護施設は、親のいない子どもたちや親と一緒に暮らせない子どもたちにとっては、家庭に代わるとても大切な居場所です。
施設の職員は子どもたちを温かく受け止めながら、家族代わりとなって安心・安全に集団生活を送れるようサポートします。
つまり、子どもたちは施設から幼稚園や学校に通い、宿題をしたり遊んだり、食事、風呂、就寝など一般家庭で普通に行われるような生活を営んでいるんです。
施設は全国で約600施設あり、その規模は、大舎(20人以上)、中舎(13~19人)、小舎(12人以下)と分けられています。
もっとも多いのは、小舎(37.9%)で、できるだけ家庭に近い環境で育てられるようにと、その数の割合が増えています。
児童養護施設で働く職員は、児童指導員や保育士、家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員、個別対応職員、心理療法担当職員、栄養士、調理員、嘱託医、事務員などです。
特に児童指導員と保育士は、子どもたちの親代わりとなって子どもたちと生活を共にし、密接に関わる存在となります。
つまり、24時間体制のシフト勤務になります。
子どもたちの生活全般を支えるとともに、一人ひとりを受け止めながら信頼関係を築いていく必要がありますが、子どもたちの抱えている事情や心の問題は複雑なため、そう簡単に簡単に心が通い合わない場合もあります。
なので、保育士だけで悩まずに、専門職がチームになって子どもを受け止め、根気よく関わりながら関係を作っていく心構えが必要です。
一般の保育園での仕事とは違って、一人一人の子どもの問題が深いので難しい仕事ではあります。
ですが、頼れる大人がいない子どもたちを守り、その生活を根本から支えていくという、とてもやりがいのある仕事と言えます。
出典:社会福祉法人 全国社会福祉協議会 全国児童養護施設協議会
障害児入所施設
障碍者入所施設は、障害のある子どもを親元から離れて入所させ、生活に必要な動作や知識、技術などを教えます。
「福祉型障害児入所施設」と「医療型障害児入所施設」があります。
福祉型は、日常生活に必要な、食事、排せつ、着脱、入浴などの介助や、身体機能や生活能力の向上のための訓練やレクリエーション活動への参加を手助けします。
医療型は福祉型にプラスして、抱えている疾病の治療や看護も行います。
入所対象となる子どもは、18歳までとなっており、入所になる経緯としては、虐待が最も多くなっています。
ただでさえ障害児は育てるのが難しいですから、親が子育てのストレスに追い詰められて虐待に走ってしまうリスクはどうしても高くなります。
また、子どもの障害の特性や程度があまりにも重いと家族では介護しきれず、一緒に暮らしていては家族の生活が成り立たなくなってしまうケースもあります。
障害児入所施設の職員である保育士は、そんな背景を持つ障害児の生活全般を24時間体制で支えます。
子どもたちにとっては、やはり施設が生活の場であり家庭代わりであり、愛情を持って温かく受け止めてくれる大人の存在は不可欠です。
さらに、一人一人に合った支援とは何かを常に考えることが必要で、障害特性を踏まえた専門的な観点からの適切な対応が求められます。
そのためにも、子どもたちのケアには、保育士だけでなく、医師、心理士、訓練士など専門職とのチームアプローチが必要なんです。
出典:障害児入所施設の在り方に関する検討会報告書(案) 厚生労働省
児童発達支援センター
児童発達支援センターとは、発達に遅れがある未就学児が、生きていくために必要な能力や技術を、週に数回、月に数回など、その子に合った頻度で通い、さまざまな活動を経験することで身につけます。
たとえば、身辺自立や認知力、社会性、コミュニケーションなどの力を、個別指導や小集団指導、機能回復訓練など子どもに適した形で継続的に行い獲得させます。
他にも、障害を持つ子どもの家族の相談に乗り、保護者の方が息抜きをしたりリフレッシュができるようなレスパイト(休息、息抜きという意味)サービスも行っています。
さらに、センターには通っていない子どもで、幼稚園や保育園で抱えている障害のある子どもについての相談にも乗ります。
当該の幼稚園や保育園などに出向いて、保育士さんに子どもとの関わり方の助言、環境設定のアドバイスなどをします。
このような機能を持つ施設が、「福祉型」といわれ、これに加えて病気の治療を行う、「医療型」もあります。
児童発達支援センターでは、子どもの発達の状態に合わせて必要な指導や訓練ができるよう、専門知識を持った職員が指導に関わります。
たとえば、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士、保育士など、それぞれの専門分野から子どもの発達の様子を見極め、必要と判断された支援を行います。
中でも保育士は、子どもの発達の遅れの様子から、どんな遊びや指導で子どもの力を伸ばせるのかを考え、個別や小集団など適切な形態によって療育を行います。
また、保護者の不安や困っていることに耳を傾け、日常生活での子どもへの関り方のアドバイスをする役割も担っています。
保育園では、子どもたちを「集団」として見るイメージですが、児童発達支援センターでは、「個」をとことん見つめてスポットライトを当てるような感じです。
一人の子どもの発達特性を多方面から深く分析し、どのような療育が必要なのかを考え実行したうえで、反省と再チャレンジを積み重ねていきます。
とにかく、個人をきめ細かく深く見ることができるのが興味深いところです。
もちろん保育士の目だけで判断するのではなく、体の動きは理学療法士、手先の動きは作業療法士、言葉については言語聴覚士、発達全般については臨床心理士など、それぞれの専門性からの見立てをもとに話し合いを重ね、子どもに最善の療育が提供できるようにします。
このような他職種との連携ができるのは、児童発達支援センターだからこそあり、非常に貴重な環境です。
保育士としてのキャリアをまた一段と高めたい方にとっては、この上ない勉強になるはずです。
児童心理治療施設
児童心理治療施設とは、心理的な不適応により、学校生活や家庭生活に困難が生じている小中学生を、短期入所や親元からの通所させることにより治療、生活改善を図る施設のことです。
対象となる子どもの状態としては、不登校、引きこもり、家庭内暴力、場面緘黙(家では話せるのに、学校など家庭以外の場面で話せなくなる症状)などがあり、情緒的にも身体的にも適切な生活が送れていない場合が多いです。
このような場合、親もわが子にどう対応したらよいかわからず、行き詰ってしまいます。
そんな状態から、子どもを児童心理治療施設に短期間入所させたり、一定期間家庭から通所させたりすることで、本人を取り巻く人的・物的な環境を変えていきます。
子どもは、施設の職員にありのままの自分を受け入れてもらうことで、安心して生活できるようになり、施設での集団生活の中で、協調性や適応力を身につけることができます。
施設には、施設の生活全般の面倒を見てくれ、話し相手になってくれる支援員としての保育士がいます。
保育士は、子どもの気持ちに寄り添いながら生活を共にすることで心の距離を縮め、安心して勉強や遊びができるように支援します。
一方、心理面の専門的なアプローチは臨床心理士が行い、個々に合わせたプレイセラピーなどによって、子どもが抱えている心の問題の解決を図ります。
つまり、施設の生活や活動のすべてが、子どもにとっては治療であり、状況の改善につながっていきます。
なかなか心を開きにくい子どもが多い中では、精神的にも大変な仕事になりますが、一人一人にじっくりと関われるため、大きなやりがいを感じられるはずです。
出典:児童心理治療施設ノアーズ・ガーデン 社会福祉法人友興会
児童家庭支援センター
児童家庭支援センターは、地域に住む子ども(18歳未満)やその家族が抱えるさまざまな問題について相談を受け、専門職の知識やスキルを用いながら、解決に向けて取り組みます。
特に、虐待や家庭生活の諸問題についての相談を受けることが多いです。
どこの一般家庭でも起こりうる、子育ての不安や悩み、家族関係の不和、生活上の問題など、幅広い相談に相談員や臨床心理士が対応します。
そして、その問題解決に向けて適切なサービスを紹介したり、具体的なアドバイスをします。
来所のきっかけとしては、親が直接相談に来る場合もありますし、保健所や保育園、幼稚園、児童相談所などが、児童家庭支援センターに相談に行くように勧める場合もあります。
また、児童相談所からの依頼を受けて、指導や経過観察が必要な家庭について指導を行います。
さらに、里親やファミリーホームの相談支援を行ったり、より望ましい支援を考えるために、子どもや家族を取り巻く関係機関(児童相談所、保育園、幼稚園、学校、保健所、医療機関など)と連絡調整を行ったりします。
そんな児童家庭支援センターでは、臨床心理士や子どもの専門家ともいえる保育士が相談に応じています。
相談内容は気軽なものから、なかなか重たい内容のものまでさまざまです。
なので、相談員である保育士は、親の話を親身になって聞きながらも、自分自身の精神もバランスを取り、気持ちをうまく切り替える意識が必要です。
もちろん、親と話すだけでなく、親が子ども同伴で来所した場合は、子どもと一緒に遊んで様子を見たり、子どもから話を聞いたりすることもあります。
子どもと打ち解け、気持ちをつかむことができるような対話力、観察力なども必要です。
このように、児童家庭支援センターの業務は、保育園のような集団保育ではなく、一人一人の親や子どもと向き合っていくことがメインになるんですね。
親や子どもの気持ちに寄り添い、今抱えている問題をどうやったら解決できるのかを共に考え、そして、必要な支援のネットワークを広げる拠点となることが求められています。
保育園以外の児童福祉施設で働くメリットとデメリット
では、以上のような保育園以外の児童福祉施設で働く場合のメリットデメリットについてお伝えしますね。
まずはメリットから行きましょう。
保育園以外の児童福祉施設で働くメリットは?
- 一人ひとりの子どもに深く関わるのでやりがいがある
- 問題を抱える子どもへの対処の仕方がわかるようになる
- 専門職と連携して働くので、その視点を身につけられる
- 保育士としてのスキルアップができ強みが増える
たとえば、「児童発達支援センター」を例にしてみましょう。
実は、私が働いたことがあるのがここなんですよ。
まず、児童発達支援センターでは、一人一人の子どもに深く関わります。
子どもが見せる問題行動を本人のせいや親のせいにするのではなく、「なぜそういった行動をするのか」という視点で深く掘り下げる必要があります。
そのような考察のもとに子どもと関わり、またその結果を踏まえた上で違う療育方法を試すなど、一人一人の子どものことを考えた対応ができるので、大きなやりがいにつながります。
そういった視点で子どもを見る習慣ができ、色々な対応法を試す経験が増えると、そういった問題を抱える子どもへのアプローチ方法がわかるようになってきます。
そんな子どもたちへの対応手段が自分の中に増えることで、いろんなケースに対して対処できるようになります。
そんな自分の引き出しが増やせるのは、児童発達支援センターには、「さまざまな専門職と連携して業務にあたる」という特徴があるからです。
たとえば、臨床心理士がいれば、子どもの現状の発達段階や問題行動の背景をひもといてくれるので、保育士としてどう関わるべきかがわかりやすくなります。
また、作業療法士がいれば、子どもの運動機能面から子どものつまずきを考察してくれ、運動面や感覚面からのアプローチを取り入れた保育を工夫できます。
そんな専門的な視点で子どもを見ると、疑問でしかないその子の行動がよくわかるようになり、療育内容も変わってきます。
もちろん専門職の方々と同じことはできませんが、「そういった子どものとらえ方もあるんだ」という視点を学べるので、次に対応するケースに活かすことができますよね。
こんなふうに、保育士のスキルを大幅にアップできるので、私自身、保育士としての強みが増した実感は大いにあります。
保育園での集団保育もできるし、個々の子どもの発達のつまずきや問題行動の背景も考察し対応できる保育士になれれば、どんな現場でもやっていけるはずですよ。
保育園のように、子どもたちを集団として動かすことは少ないので、集団保育に苦手さを感じる保育士の方にも向いています。
保育園以外の児童福祉施設で働くデメリットは?
- 24時間体制の場合は夜勤があるので、体力的にキツイ
- 問題を抱える子どもや親に対応するため、精神的に疲れる
保育園以外の児童福祉施設で働くデメリットは、施設の目的や特徴にもよりますが、多くは24時間体制を取っていることです。
それによって、どうしても夜勤が発生してしまいます。
夜勤を含めたシフト制で働くことが、体力的にキツイと感じる方もいます。
ただ、それさえクリアできれば、「平日に休みが欲しい」「平日の昼間に自分の時間が欲しい」という方には、むしろ都合よく働ける環境と言えます。
もう一つのデメリットは、問題のある子どもや親と対応することが多いため、精神的に消耗しやすいことです。
こちらが良かれと思ってやったことや言ったことを素直に受け止めてもらえなかったり、思いがけず関係がこじれたりする場合もあります。
なので、自分の力不足に落ち込んだり自信を無くしたり、精神的に追い詰められてしまう方もいます。
ただ、これについても自分の気持ちを上手に切り替える方法を身につけ、また自分一人で問題を抱え込まず、職員同士で連携することで乗り越えられることも多いです。
保育園であっても、対応が難しい子どもや親はいますし、それこそ職員同士の関係が悪ければ、全く相談もできずに一人追い詰められてしまう保育士の方は多いです。
そう考えると、どこに勤めていても精神的な負担を抱える可能性はありますし、結局はそこの職員の人間関係の良し悪しが大きく影響すると言えるのではないでしょうか。
ちなみに、私もこれまで私立保育園や公立保育園で働いていたことがありますが、児童発達支援センターでの職員関係が1番よかったと感じています。
色々な職種と関わり合って仕事をするので、保育士同士の派閥などもありませんでした。
もちろん、困難ケースはあるものの精神的につらくなるようなことはなく、職員同士の連携を持って対応できたので、やりがいを持って働けましたよ。
まとめ

保育園以外の児童福祉施設でも、保育士資格を活かして働ける場があることがおわかりいただけたでしょうか。
施設ごとに対象となる子どもや親が違うので、それによっても保育士の働き方や仕事内容は変わってきます。
どの施設も困難を抱えている子どもや親を支援する重要な役割を担っているからこそ、そこで保育士として働くことで、大きなやりがいを感じられますよ。
ただ、保育園に比べて施設数自体が少ないので、求人数も少ない傾向にあります。
なので、ぜひ保育士転職サイトに登録して、どのような施設の求人がどれくらいあるのか聞いてみることをおすすめします。
もし、自力で探す場合も、これはと思う施設のホームページの求人情報をこまめに確認することが大切です。
求人がないかどうか、自分から問い合わせてみるのもいいかもしれませんね。
保育園以外の児童福祉施設で働けるのは、保育士資格があればこその特権ともいえます。
保育士のスキルを高めたい方、また人生の視野を広げたい方には、おすすめの転職先ですよ。
ぜひ検討してみてくださいね。